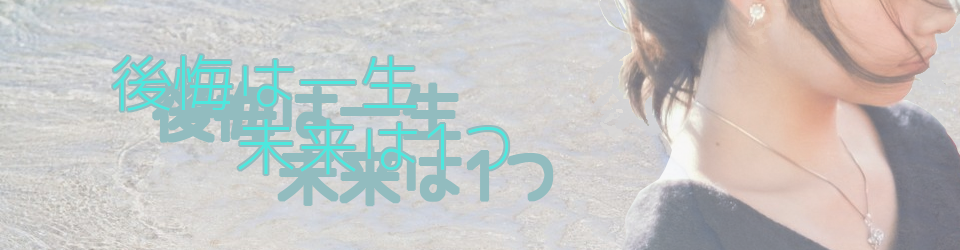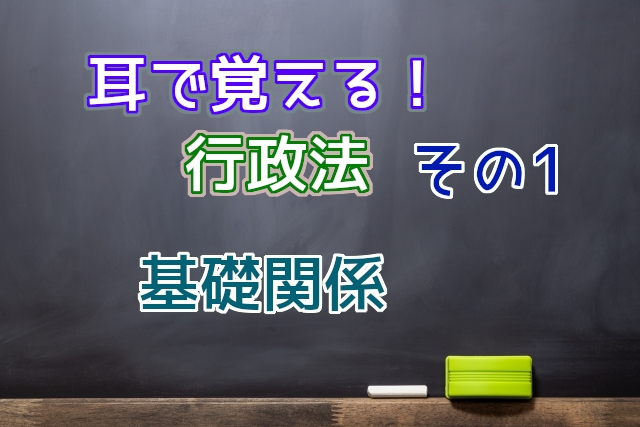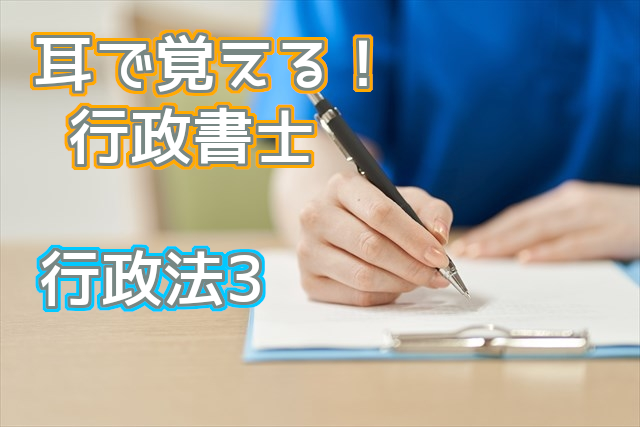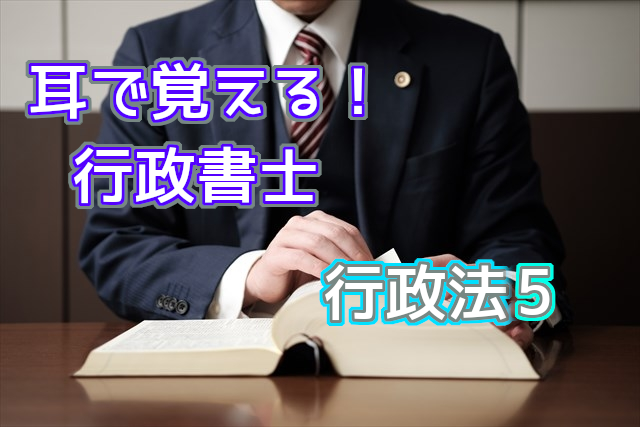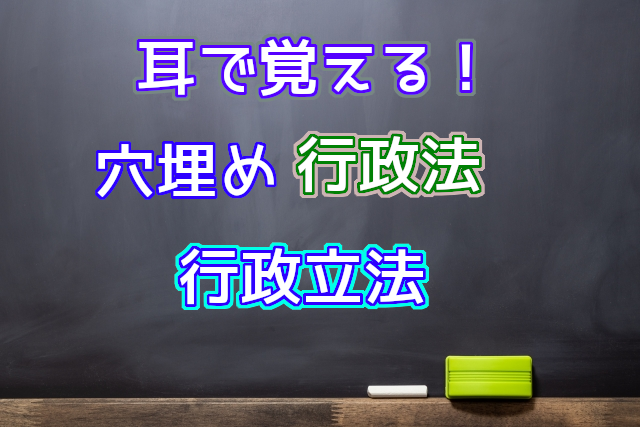
法規命令とは、行政機関が定める国民一般の【A】に関係する「法規範」の事で、行政機関だけでなく【B】も拘束し、裁判規範として機能する。(外部的効果を有する)
法規命令の形式の例で、以下を制定するのはどこ?
【A】:内閣
【B】:内閣総理大臣
【C】:各省大臣
【D】:各庁長や各委員会
法規命令は【A】命令と【B】命令に分かれる。
【A】命令:法律を前提とし、当該法律を具体的に実施する為必要な事項を定める命令。法律の根拠は【C 必要or不要】
【B】命令:法律の委任により新たに国民の権利義務内容を定める命令。法律根拠は【D 必要or不要】。
(政令で定めるところにより。等、授権法律で形式について指定されるのが多い。)
委任事項を【A】的【B】的に定める場合、憲法枠内で認められた委任となるが、白紙委任は憲法【C】条に違反する為許されない。
行政内部で用いられ、国民の権利義務に関わらない行政規範のことを【A】という。この形式は【B】や通達、内規・要綱等があり、公示が必要な場合は【C】の形式をとることが多い。また、【A】は法律の根拠【D ありorなし】で定立できる。
上級機関が関係下級機関や職員に対し、職務権限行使の指揮などの為に発する命令を【A】という。
上級機関は組織法上の権限に基づき、法律の根拠を【B 要さず、要して】【A】を発することができる。
通常【A】という形式で行われる、ある処分に対する取扱いを統一するために発する法令解釈の基準を【C】という。
通達に関し、【A】は必ずしも要件とはならないが、情報公開法下では公開請求の対象なので、法定の非公開事由でなければ秘密通達は許されない。
通達は局長・部長など【B】も発することができる。事務処理の全国的統一の為発せられた場合で、これに反する措置を行った場合、他の、通達に沿って行った措置との関係では【C】違反となり違法となる余地がある。
仮に違法な通達でも、その命令に【D】がなければ従う義務があり、服従拒否の理由で【E】が適法となる場合がある。
いかなる場合に処分を行うか、行政法規が行政庁に判断をゆだねている場合に裁量権の行使の仕方を定めるもののことを【A】という。
この【A】には、行政手続法上の【B】基準・【C】基準などがある。
裁量基準により解決が得られない場合もあるため個別の事案の性質に照らし、合理的理由があれば、裁量基準と異なる判断は【A 許されるor許されない】。
ある処分が裁量基準に違背したとしても、当不当の問題であり、当然に【B】とはならないが、合理的理由がなく裁量基準を適用しないのは【C】に反し【B】となる。
国・地方公共団体が私人に補助金など【A】を給付することに関する基準を【B】という。
【B】は内部基準としての行政規則なので、これに基づいた申請は【C】に基づいた申請ではない。そのため【B】に基づいた申請が拒否された場合に、(行政事件訴訟法)【D】訴訟や【E】訴訟は提起できない。
指導要綱・・・【F】や【G】の適正化のため、【H】が定立する行政指導基準。これは行政規則にすぎないので、住民を拘束する【I】にはならないとされている。