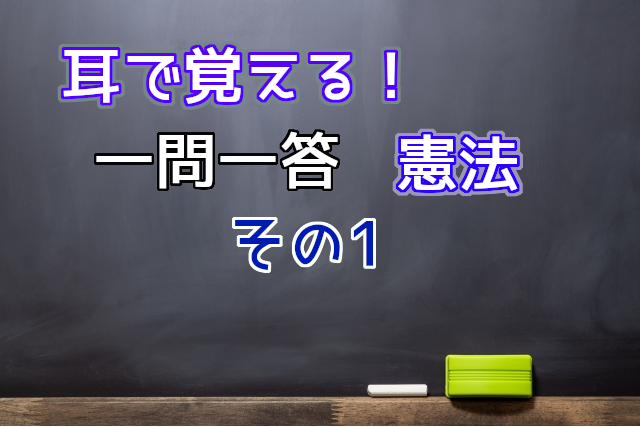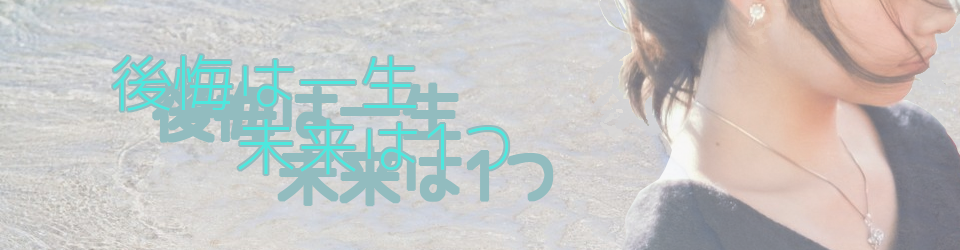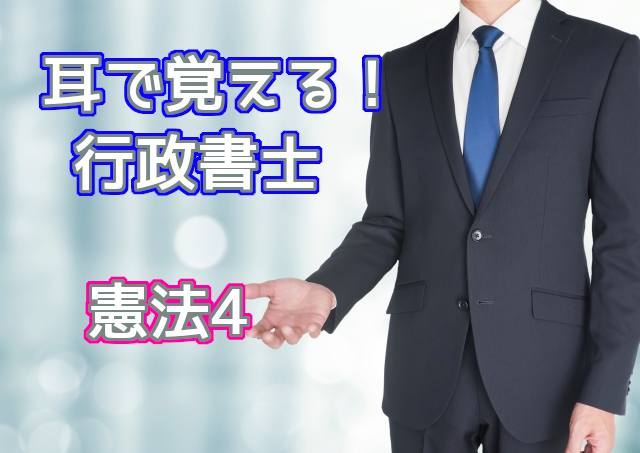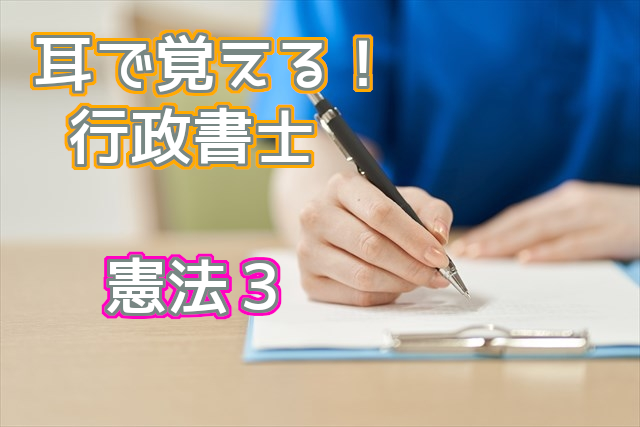※過去問で重複する問題がある可能性があります。
ここからチャンネル登録をしておけます。あとで探す手間が省けます。→
問1
憲法概念はその存在様式によって区分することができる。憲法という法形式をとって存在している法を「形式的意味の憲法」と呼び、法形式に関わらず国家の組織や作用に関する基本的規範を「実質的意味の憲法」と呼ぶ。
1の正解はここ
〇
形式的意味の憲法:憲法と呼ばれる成文の法典
実質的意味の憲法:成文・不文・法形式を問わず国の統治の基本を定めた法
問2
形式的意味の憲法の効力は他の法規範より優越する。多くの国ではこの優越性を現実に保障するため裁判所による違憲審査制を採用しているが、法令の合憲性について議会が最終的に判断するという制度が憲法の形式的優位性と矛盾するとはいえない
2の正解はここ
〇
憲法は最高法規であり、国法秩序においても最も強い形式的効力を持ちます。この最高法規性は多くの国で違憲審査制度が採用されています。どの機関が違憲審査を行うかは別なので、議会が違憲審査を行ったとしても憲法の形式的優位性と矛盾しません。
問3
「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」を区別することができる。1789年フランス人権宣言の有名な一説「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会はすべて憲法を持つものではない」は、前者の趣旨を示したものである。
3の正解はここ
×
フランス人権宣言16条「人権保障と権力分立の自由主義に基づく憲法の必要性」を規定しました。
自由主義に基づいて定められる国家の基礎法を「立憲的意味の憲法」と呼びます。
フランス人権宣言は後者の意味を示しています。
問4
形式的意味の憲法にはいかなる内容を盛り込むことも可能だが、歴史的には立憲主義の成文化を求める動きが憲法典の普及を促進した。日本国憲法はこの経緯を踏まえ、憲法の形式的優位性の実質的根拠を示すため、第10章「最高法規」中に公務員の憲法尊重擁護義務を定める第99条を置いている
4の正解はここ
×
憲法が最高法規性としての実質的根拠は「憲法目的が人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する」点にあります。公務員の憲法尊重擁護義務が形式的最高法規性を示しているわけではありません
問5
国家統治の基本を定めた法としての憲法を【固有の意味の憲法】と呼び、国家権力を制限し国民の権利を保障するという思想に基づくものを【立憲的意味の憲法】と呼び、それぞれ区別する事がある。これは憲法の内容に着目した区別で、憲法の存在形式とは無関係である
5の正解はここ
〇
固有の意味の憲法:国家統治の基本を定めた法
立憲的意味の憲法:基本的人権の保障、国民主権、権力分立という基本的原理を内容とする。
これらの区別はその内容に着目しています
問6
憲法と呼ばれる憲法典を【形式的意味の憲法】と呼び、【実質的意味の憲法】と区別する事がある。この意義は、憲法典に書かれるべきことがかかれないことがあり、逆に本来憲法内容になるべきでないものが法典に書かれることがある点に注意を促すことにある。
6の正解はここ
×
成文憲法典を形式的意味の憲法と呼びます。そして実質的な国家の基本法を実質的意味の憲法と呼び区別する事があります。これは憲法典がない国にも実質意味の憲法は存在することになり、また、憲法典の中にも実質的意味の憲法とは言えない規定が存在しうることになります。
問7
憲法改正に法律改正より困難な手続が要求される憲法を硬性憲法、法律改正と同じでよいものを軟性憲法と区別する事がある。
憲法の最高法規性は憲法が「硬性憲法」として国家秩序において最も強い形式的効力を持つ点に求められるので、憲法がいかなる基本価値を体現しているかは関係がない
7の正解はここ
×
硬性憲法として最も強い形式的効力を持つのはその重要な規範内容に鑑みてのことであり、最高法規性の実質的根拠は憲法が国民に基本的人権を保障しているところにあります。
問8
硬性憲法の原則を重視する立場をとっても、憲法の空白を埋める事実が反復・継続された場合に国家機関を政治的に拘束する憲法慣習の成立を認めることができる。
8の正解はここ
〇
慣習憲法は不文法形式の憲法で、憲法改正手続きとは関連がありませんので、硬性憲法の原則を重視しても、憲法慣習を認めることができます。
問9
判例が後の裁判を法的に拘束するという立場をとるならば、法律の合憲性に関する最高裁判所の判例を変更することは、後の最高裁場所であっても許されない
9の正解はここ
×
判例は一般に後の裁判を拘束すると解されますが、法律の合憲性に関する最高裁の判例を後の最高裁が変更するのは認められます。
裁判所法10条
問10
条約の国内法的効力は憲法に劣るという立場をとるならば、裁判所が立法事実の存否を判断する為の資料として国際人権条約を参照することは許されない
10の正解はここ
×
憲法優位説:条約は憲法に反しない限り効力を有する。
憲法優位説に立っても、国際協調主義の規定は妥当し、条約の誠実遵守を宣言しています。
裁判所が立法事実の存否を判断する材料として国際人権条約を参照することはできます。
憲法98条2項
問11
日本国憲法前文は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原理を明らかにしており、憲法の一部をなすものであって当該規定を根拠に裁判規範性が認められている
11の正解はここ
×
裁判規範性:当該規定を直接根拠とし、裁判所に救済を求めることができる。というもの。
昭48.9.7
日本国憲法前文は法規範性を有しますが、裁判規範性は認められていません。
問12
法の支配は、人による支配を排斥し、権力を法で拘束することで国民の権利・自由を保障することを目的とする原理である。
問13
法の支配は、法律による行政の原理を意味し、その法律自体の内容は問わない原理である。
13の正解はここ
×
法の支配は法律内容は合理的なものである必要があります。
問14
日本国憲法も、憲法の最高法規性、基本的人権の保障、特別裁判所の設置の禁止、裁判所による違憲立法審査権等からして法の支配の原理に立脚しているといえる
問15
第二次世界大戦以前には人権を国際的に保障する制度は構築されておらず、第一次世界大戦後に国際連盟が結成されたが、人権問題は専ら国内問題とされていた
15の正解はここ
〇
国内問題不干渉義務があり、人権は国内問題とされていました。
問16
第二次世界大戦後、国際連合において採択された世界人権宣言は、国際社会における人権に関する規律の中で最も基本的な宣言で、法規範性を有している
16の正解はここ
×
世界人権宣言は、世界の人権に関する規律の中でもっとも基本的意義を有しているが、宣言であり法規範性はありません。
問17
国際連合において採択された国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎としこれを条約化したもので法規範性を有している
17の正解はここ
〇
国際人権規約は、条約化したものであるため、加盟国を直接拘束する条約のため法規範性を有しています。
問18
憲法前文第3段「自国の主権を維持し」という場合の主権は、対外的な独立性に重点を置いた意味で使われる。
18の正解はここ
〇
最高独立性を意味し使われています。内には最高、外には独立ということ。
問19
憲法第1条「主権の存する日本国民の総意」は、国の政治のあり方を最終的に決定する権力又は権威を意味する
問20
憲法改正手続における国民投票は、国民主権の権力的な契機の表れといえる
20の正解はここ
〇
憲法改正権:制度化された制憲権と呼ばれます。
2022/10/19更新
問21
日本国憲法前文は「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つの基本原理を明らかにしており、憲法の一部をなすのであって当該規定を根拠に裁判所に救済を求めることができるという意味で、裁判規範性が認められている。
21の正解はここ
×
日本国憲法前文では3つの原理「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」を明らかにしているので、ここはOK。そして法規範性も有しています。
ただ、前文は直接根拠を当該の規定とし、裁判所に救済を求める(裁判規範性)を有するとは解されていません。
問22
憲法が成文の憲法を指す場合に「形式的意味の憲法」と呼ばれるが、この意味の憲法は、その内容において人権保障に関する規定がふくまれているかどうかを問わない。
22の正解はここ
〇
形式的意味の憲法→憲法と呼ばれる「成文の法典」を意味します。(憲法典とも言います)
これには内容までは問われません。
問23
国家であれば、権力組織や構造が定まっていると考えられ、この意味で全ての国家は憲法を持つといわれるが、この場合の憲法は「固有の意味の憲法」と呼ばれる
23の正解はここ
〇
固有の意味の憲法→国家統治の基本を定めた法としての憲法。政治権力組織との関係を規律する規範であり、この意味で言えば、どんな時代だろうと国家だろうと存在する事になります。
問24
1789年フランス人権宣言第16条において、権利の保障が確保されず権力の分立が定められていない社会は、全て憲法を持つものではない旨が示されているが、この場合の憲法は「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と呼ばれる。
24の正解はここ
〇
フランス人権宣言16条→【権利保障が確保されず、権力分立が定められていない社会はすべて憲法をもつものではない】。
「立憲的意味の憲法」「近代的意味の憲法」と呼ばれます。これは、自由主義に基づく国家の基礎法を意味し、「専断的権力を制限」し「広く国民の権利を保証」する【立憲主義の思想】に基づきます。
問25
第二次世界大戦以前は人権を国際的に保障する制度はなく、第一次世界大戦後に国際連盟が結成されたが、人権は専ら国内問題とされていた。
25の正解はここ
〇
第二次世界大戦前以前は【国際連盟規約15条8項、国内問題不干渉義務】により、人権は国内問とされていました
問26
第二次世界大戦後、国際連合で採択された世界人権宣言は、国際社会における人権に関する規律の中で最も基本的な宣言であるので、法規範性を有している
26の正解はここ
×
世界人権宣言は、この後の国際連合で結ばれた人権条約の基礎となっており、世界の人権に関する規律で最も基本的な意義を有していますが、これは【宣言】なので法規範性はありません。
問27
第二次世界大戦後、国際連合において採択された国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものであり法規範性を有している
27の正解はここ
〇
1966年採択の国際人権規約は世界人権宣言の内容を基礎とし、条約としたものなので法規範性を有しています。世界人権宣言と違って加盟国を直接拘束します。
問28
憲法の国民主権の原理での国民とは、最高裁判所の判例が示すところによると、主権が日本国民に存するとする憲法前文及び第一条の規定に照らし、日本国憲法の国籍を有する者を意味するとされる。
28の正解はここ
〇
判例より、憲法15条1項は国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存する事を表明したものとし、国民とは日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味するのは明らかである。としました。
問29
主権という言葉は多義的で、国民主権・国家主権の他、国家権力そのものを意味する場合もあり、憲法9条第1項及び第41条で使われている国権とは、この国家権力そのものを表すものとして使われている
29の正解はここ
〇
「主権」は【国家権力そのもの】を意味する場合もあります。憲法9条「国権の発動たる戦争」という表現は【国家権力そのもの】を意味すると解されています。また、憲法41条「国権の最高機関」とありますが、この国権も【国家権力そのもの】を意味すると解されます。
問30
国民主権原理を宣明する憲法では、国民の代表者を選定する選挙制度は民主主義の根幹を成すものである。憲法改正における国民投票の具体化といえるものであるから、その投票権者の要件を公職選挙法が定める選挙権者の要件と異なって定める法律は違憲である
30の正解はここ
×
憲法の原理の1つとされる国民主権は、国民に国政の最高決定権が帰属することを意味するので、その代表者を国民が選定する選挙制度は民主主義の根幹であるといえ、憲法改正が国民投票によって成立する事は国民主権の具体化といえます。ただし、憲法改正における投票権者の要件を公職選挙法が定める選挙権者の要件と異なって定める法律が【ただちに】違憲となるわけではありません。
問31
国民主権の観念は、本来、君主主義との対抗関係の下で生成し主張されてきたものである。
31の正解はここ
〇
国民主権の概念は君主主権との対抗関係のもとで社会契約論を背景に、人民主権として形成されてきたものです。これを踏まえて国民主権の担い手主体は実在する君主に対抗することができる具体的な人民であり、抽象的なものや特別な資格をもつ君主でもないとなります。
問32
主権の権力性の契機において、主権の主体である国民は有権者を指す。しかし国民を有権者ととらえることは、必ずしも憲法が直接民主主義を採用しているという結論を帰結するわけではない。
32の正解はここ
〇
国民主権の原理は二つの要素があり、一つは正当性の契機であり、もう一つは国の政治のあり方を最終決定する権力を国民が行使するという権力的契機です 。国民を有権者と捉えることは国民が政治に参加する制度である民主制と密接に結びつく。が、民主制のうち国民自身が直接国の政治に関する意思決定を行う直接民主制を採用するか、国民は事故が占拠した代表者を通じて間接的に政治的意思決定を行う間接民主制を採用するかは制度のメリットデメリットを比較考量した上で決定されるのであり国民を有権者と捉えることで決定されるものではありません。
問33
主権の正当性の契機において、主権の主体である国民は全国民を指す。国民を全国民と捉えると、国民主権の原理は命令的委任に拘束された国民代表制を要請することになる。
33の正解はここ
×
国民主権の原理の二つの要素のうち国家権力を正当化し権威づける根拠は究極において国民にあるという要素が重視されます。主権の保持者としての国民は有権者に限定されず全国民(国籍保持者の総体)となります。国民を全国民と捉えた上で国民代表制を採用すると代表者は特定の国民ではなく全国民の利益となるよう権限を行使しなければならなくなるため、国民を全国民と捉えたとしても代表者が特定の国民の意思に法的に拘束される命令的委任に拘束された国民代表制が要請されるわけではありません。
問34
その行為自体が各目的・儀礼的な国事行為について、天皇は自らの判断に基づき内閣の助言と承認を拒むことは許されない
34の正解はここ
〇
天皇は国事行為について、各目的、儀礼的なものでも権能を有しない以上は内閣の助言と承認を拒むことは許されません。【天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である】という憲法は、天皇が国政に関する権能を持たないことを意味します
問35
憲法は天皇の無答責を明文で規定しないので、内閣の助言と承認のもとで行われた天皇の国事行為であっても、内閣の責任のほかに天皇が責任を負う事があり得る
35の正解はここ
×
天皇は責任を負いません。【天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う】と定められ、内閣は、天皇の行為の結果について責任を負い、天皇は無答責となります
問36
国政に関する権能を天皇に付与しない限り、憲法で定められている国事行為以外の行為について、新たな国事行為として法律で定める事も許される
36の正解はここ
×
憲法により、【天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない】となります。これにより天皇は、法律をもってしても、憲法に定める以外の国事行為はできません
問37
法の支配は「人による支配」を排斥し、権力を法で拘束することで国民の権利・自由を保障する事を目的とする原理である。
37の正解はここ
〇
【法の支配の原理】は、中世の法思想により、英米法根幹として発展した基本原理となります。「専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することで国民の権利・自由を擁護する目的」があります。
問38
法の支配は「法律による行政」の原理を意味するもので、その法律自体の内容は問わない原理である
38の正解はここ
×
法の支配は、立憲主義の進展とともに「権利自由を制約する法律内容は国民自体が決定する建前である原理」であることが明確で【民主主義】と結合すると考えられています。
また、法治国家とは民主的制度と結び付いて構成されてるわけではありません。法治国家で言う「法」とは、内容と関係のない形式的法律に過ぎませんので、法律内容が合理的なものである必要があります。
問39
日本国憲法も、憲法の最高法規性・基本的人権の保障・特別裁判所の設置禁止・裁判所による違憲立法審査権などからして「法の支配」の原理に立脚しているといえる
39の正解はここ
〇
日本国憲法は法の支配の原理に立脚すると考えられます。「憲法の最高法規性」「基本的人権の保障」「裁判所による違憲立法審査権」があげられます
問40
憲法前文第三段「自国の主権を維持し」 という場合の主権は対外的な独立性に重点を置いた意味で使われる
40の正解はここ
〇
「自国の主権を維持し」は最高独立性に重点を置いた意味で使われています。(内側にあっては最高で外側に対しては独立ということ)
問41
憲法第1条「主権の存する日本国民の総意」 という場合の主権は、国の政治のあり方を最終的に決定する権力または権威を意味する
41の正解はここ
〇
「主権の存する日本国民の総意」にいう主権とは最高決定権という意味で使われています。(最高決定権:国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威)
問42
憲法第96条第1項規定の憲法改正手続きにおける国民投票は、 国民主権の権力的な契機の表れと言える
42の正解はここ
〇
憲法改正権は制度化された制憲権とも言われ、国民主権の権力的な契機の表れとなります。
問43
日本国憲法前文【われらはいづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的であり、この法則に従う事は、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国責務であると信ずる】にある主権は「国家の統治権」を意味する
43の正解はここ
×
国民主権の概念は一般として、【国家の統治権】【国家権力の属性としての最高独立性】【国政について最高決定権】としての意味に使われます。憲法前文3段での「自国の主権」は【国家権力の属性としての最高独立性】を意味します
問44
国民主権の意義を、国家が支配権力を行使する権威のよりどころが国民に由来する事と解する立場からすると、国民主権の原理は、国家権力の行使が全国民の名のもとで行われるべきことを意味するに留まり、実際に国家の意思決定に国民の意思が的確に反映されるような仕組みを作ることまでは要請されない
44の正解はここ
〇
国民主権の異議をナシオン主義(国家権力の正当性が国民に由来する事と解する立場)からすると、国の政治は国民の利益となるように行われれば足り、個々の具体的な国民の意思が国政に反映される必要はないと考えられるため実際に国家の意思決定に国民の意思が的確に反映される仕組みを作ることまでは要請されません
問45
ポツダム宣言8項には「日本国の主権は本州、北海道、九州及四国並びに我らの決定する諸小島に局限せらるべし」とあるが、ここに言う主権は日本国憲法第1条にいう主権の意味とは異なる
45の正解はここ
〇
ポツダム宣言8項での「主権」は【国家の統治権】の意味ですが、日本国憲法1条の「主権」は【国政についての最高決定権】です
問46
日本国憲法の国民主権原理が明治憲法の天皇主権の指定として表明されたものだという趣旨からすると、日本国憲法下において少なくとも天皇は国民ではないことは明らかである。
46の正解はここ
×
国民主権原理を明治憲法の天皇主権を否定する趣旨と考えても、天皇が国民に含まれると考える事は出来ます
問47
絶対王政の時代には、国家の主権と国王の主権を区別することに意味がなく現に両者は一体的に捉えられていた
47の正解はここ
〇
絶対王政のような専制君主制国家では主権概念は「国家の主権」かつ「君主の権力」という形で統一的に理解されており、その後の君主制の立憲主義化に伴い君主の権力と国家権力とは区別して考えられるようになりました
問48
ポツダム宣言第8項「日本国の主権は本州、北海道、九州及四国並びに吾等の決定する諸小島に局限せらるべし」にいう主権は、対外的独立性の意味の主権であるとされている
問49
一般に連邦国家では、主権は各州に帰属し連邦は州より委譲された範囲でしか権限を行使し得ないため、連邦国家を主権国家と呼ぶことはできないとされている
問50
統治権という意味での主権は国家に属すると考える国家法人説は、君主主権と国民主権のどちらにも結びつき得る考え方である
50の正解はここ
〇
国家法人説は、「君主主権か国民主権かは国家の最高意思を決定する最高機関の地位に君主がつくか、国民がつくかの違いにすぎない」ため、君主主権あるいは国民主権どちらにも結びつきえます。(国家法人説とは、国家を法的に一つの法人として国家は意思を有する権利(統治権)の主体であって、君主議会裁判所は国家という法人の機関であるとする理念のことです)