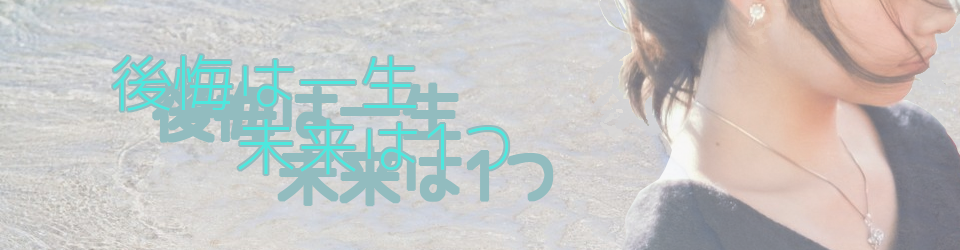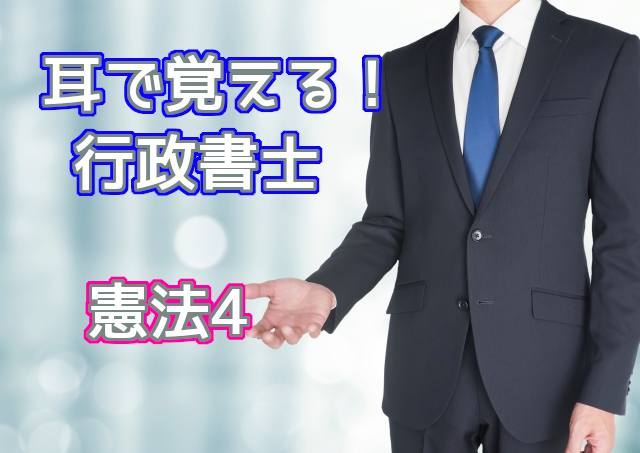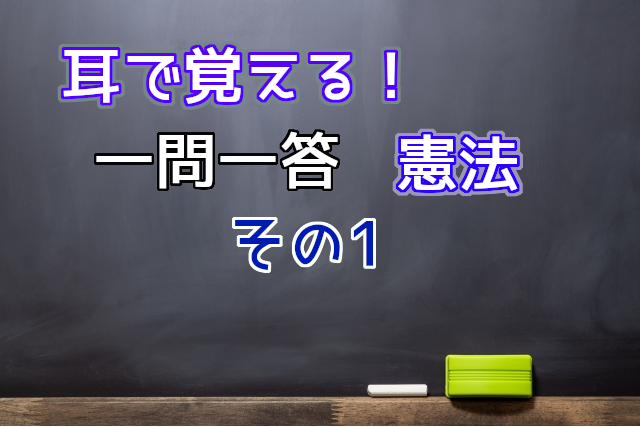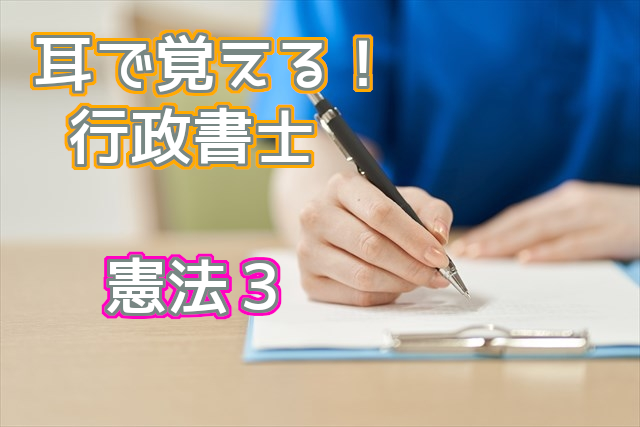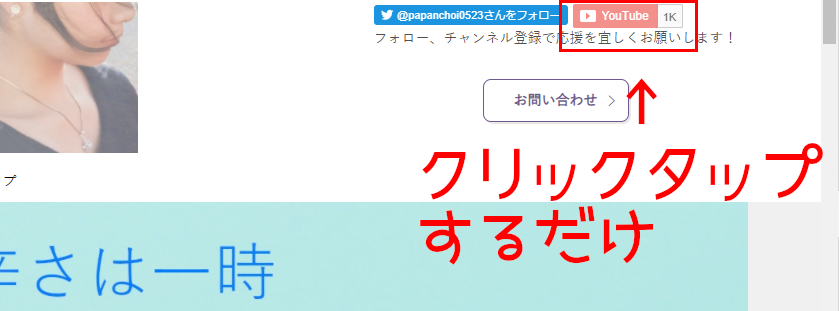
次の最高裁の一節で正しいものを選べ
最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂【A】の制度と見ることが出来る。それ故本来ならば【B】を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に【B】されるものとしてもよかったのである。それを憲法は投票数の過半数とした処が他の【A】の制度と異なるけれどもそのため【A】の制度でないものとする趣旨と解する事は出来ない。只【B】を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採っただけで根本の性質はどこ迄も【A】の制度である。このことは憲法第七九条三項にある。~~国民が【B】すべきか否かを決定する趣旨であって所論のように【C】そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。
1 憲法によれば国務大臣を【C】するのは内閣総理大臣である
2 憲法によれば内閣総理大臣は任意に国務大臣を【A】することができる
3 憲法によれば公務員を【A】し、及びこれを【B】することは国民固有の権利である
4 【A】は罷免、【C】は任命の語句が入る
5 【A】はレファレンダムと呼ばれ地方公共団体の首長などに対しても認められる
法の下の平等に関し妥当でないのはどれ
1 憲法が条例制定権を認める以上、条例の内容をめぐり地域間で差異が生じるのは当然に予期されるから一定の行為の規制につき、ある地域でのみ罰則規定が置かれている場合でも地域差ゆえに違憲ということはできない
2 選挙制度を政党本位のものにすることも国会の裁量に含まれるので、衆議院選挙において小選挙区選挙と比例代表選挙に重複立候補できるものを、一定要件を満たした政党等に所属するものに限る事は憲法に違反しない
3 法定相続分について嫡出性の有無により差異を設ける規定は相続時の補充的な規定であることを考慮してももはや合理性を有するとは言えず憲法違反である
4 尊属に対する殺人を高度の社会的非難に当たるものとして一般殺人とは区別して類型化し、法律上刑の加重要件とする規定を設けるのは不合理な差別として憲法違反である
5 父性の推定の重複を回避し父子関係をめぐる紛争を未然に防止するため、女性にのみ100日を超える再婚禁止期間を設けるのは立法目的との関係で合理性を欠き憲法違反である。
信教の自由・政教分離に関し最も妥当なのはどれ
1 憲法が国及びその機関に対し禁ずる宗教的活動とは、その目的・効果が主教に対する援助・助長・圧迫・干渉にあたるような行為あるいは宗教と過度の関わり合いを持つ行為のいずれかをいう
2 憲法は宗教と何らかの関わり合いのある行為を行っている組織ないし団体であれば、これに対する公金の支出を禁じているが、宗教活動を本来の目的としない組織は該当しない
3 神社が主催する行事に際し県が公費から比較的低額の玉串料等を奉納する事は、慣習化した社会的儀礼であると見ることが出来るので当然に憲法違反とは言えない
4 信仰の自由の保障は私人間にも間接的に及ぶので、自己の信仰上の静謐(せいひつ)を他者の宗教上の行為によって害された場合、原則、かかる宗教上の感情を被侵害利益として損害賠償や差し止めを請求するなど法的救済を求めることが出来る
5 解散命令などの宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、そこに何らかの支障を生じさせるならば、信教の自由の重要性に配慮し、規制が憲法上許容されるか慎重に吟味しなければならない
住民基本台帳ネットワークシステムについて、憲法13条の保障する自由を侵害するものではない旨の判示について、判決の論旨に含まれないのはどれ
1 住基ネットにおけるシステム技術上・法制度上の不備の為に本人確認情報が法令等の根拠に基づかず、または正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示・公表される具体的な危険が生じているということはできない
2 住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等は法令等の根拠に基づき住民サービスの向上および行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものという事が出来る
3 氏名・生年月日・性別・住所という4情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とは言えない
4 自己に関する情報をコントロールする個人の憲法上の権利は、私生活の平穏を侵害されないという消極的な自由に加えて、自己の情報について閲覧・訂正ないし抹消を公権力に対して積極的に請求する権利も包括している
5 憲法13条は国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しており、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有する
立法に関して必ずしも明文規定されていないのはどれ?
1 衆議院で可決し参議院で異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の2/3以上の多数で再び可決した時は法律となる
2 両議院は各々その総議員の1/3以上の出席が無ければ議事を開き議決することが出来ない
3 両議院の議員は議員で行った演説、討論または表決について院外で責任を問われない
4 内閣は法律案を作成し、国会に提出してその審議を受け議決を経なければならない
5 出席議員の1/5以上の要求があれば各議員の表決は会議録に記載しなければならない
憲法訴訟における違憲性の主張適格が問題となった第三者没収に関する判例で法廷意見で正しい組み合わせはどれか
A 第三者の所有物の没収は所有物を没収される第三者にも告知・弁解・防禦の機会を与える機会が必要であり、これなしに没収することは適切な法律手段によらないで財産権を侵害することになる
B かかる没収の言渡を受けた被告人はたとえ第三者の所有物に関する場合でもそれが被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の意見を理由として上告をすることが出来る
C 被告人としても、その物の占有権を剥奪され、これを使用・収益出来ない状態に置かれ、所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等、利害関係を有する事が明らかであるから、上告により救済を求めることが出来ると解すべきである
D 被告人自身は本件没収によって現実の具体的不利益を蒙ってはいないから現実の具体的不利益を蒙っていない被告人の申立に基づき没収の違憲性に判断を加えることは、将来を予想した抽象的判断を下すものに外ならず、憲法81条が付与する違憲審査権の範囲を逸脱する。
E 刑事訴訟法では被告人に対して言い渡される判決の直接効力が被告人以外の第三者に及ぶことは認められていない以上、本件の没収の裁判によって第三者の所有権は侵害されていない
衆議院の解散について妥当なものはどれ?
1 衆議院議員総選挙は衆議院議員の任期が満了した場合と衆議院が解散された場合に行われるが、実際の運用では任期満了による総選挙が過半数を占め、解散による総選挙は例外となっている
2 内閣による衆議院の解散は高度の政治性を有する国家行為であるから、解散が憲法の明文規定に反して行われるなど、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き司法審査は及ばないとする
3 最高裁判所が衆議院議員選挙における投票価値の不均衡について憲法違反の状態にあると判断した場合にも、内閣の解散権は制約されないとするのが政府見解だが、実際には不均衡を是正しないまま衆議院が解散された例はない
4 衆議院が内閣不信任案を可決し、または信任案を否決した時、内閣は衆議院を解散できるがこの場合、内閣によりすでに解散が決定されているので天皇は内閣の助言と承認を経ず、国事行為として衆議院議員選挙の公示を行うことが出来る
5 天皇の国事行為は本来厳密に形式的儀礼的性格のものにすぎないと考えるならば、国事行為としての衆議院の解散宣言について内閣が助言と承認の機能を有しているからといって内閣が憲法上当然に解散権を有していると決めつける事は出来ない
文章内「」の趣旨に最も適合しないのは?
議員が独立的機関であるなら、みずからの権能について行使・不行使をみずから決定しえなければならない。議員の権能行使は議員の自律にまかせられるを要するけれども、憲法典は通常、議員がこのような自律権を有する事を明文で規定しない。独立の地位をもつことの当然の帰結だからである。これに比べ制度上の意味の限定的な議員の不逮捕特権や免責特権がかえって憲法典に規定されるのは、それが独立機関の構成員とされてなくても議員の自律権は議員の存在理由を確保するために不可欠で議員特権などより重い意味を持っている。
しかし日本国憲法典をじっくり味読するなら「議員に自律権ある事を前提とし、これある事を指示する規定」がある。
1 両議院は各々その会議その他手続及び内部の規律に関する規則を定めることが出来る
2 両議院は各々国政に関する調査を行いこれに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することが出来る
3 両議院は各々その議長その他役員を選任する
4 両議院は各々その議員の資格に関する争訟を裁判する
5 両議院は各々院内の秩序をみだした議員を懲罰することが出来る
表現の自由の規制に関し妥当でないのはどれ?
1 表現の内容規制とは、ある表現が伝達しようとするメッセージを理由とした規制で政府の転覆を煽動する文書の禁止、国家機密に属する情報の公表の禁止などがある
2 表現の内容を理由とした規制であっても高い価値の表現でないことを理由に通常の内容規制より緩やかに審査され、規制が許されるべきだとする場合があり、営利を目的とした表現や人種的憎悪をあおる表現がある
3 表現内容中立規制とは、表現が伝達しようとするメッセージの内容には直接関係なく行われる規制であり、学校近くの騒音の規制や一定の選挙運動の制限などである
4 表現行為を事前に規制する事は原則として許されないとされ、検問は判例によれば絶対的に禁じられるが裁判所による表現行為の事前差し止めは厳格な要件の下で許容される場合がある
5 表現行為の規制には明確性が求められるため表現行為を規制する刑罰法規の法文が漠然不明確だったり過度に広汎であったりする場合、そうした文言の射程を限定的に解釈し合憲とすることは判例によれば許されない
A~Eに入る語句で正しい組み合わせはどれ
未決勾留は刑事訴訟法の規定に基づき逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として被疑者又は被告人の【A】を監獄内に限定するものであって、勾留により拘禁された者はその限度で【B】的行動の自由を制限されるのみならず前記逃亡又は罪証隠滅の防止の目的の為必要かつ【C】的な範囲においてそれ以外の行為の自由も制限されることを免れない・・・また、監獄は多数の被拘禁者を外部から【D】して収容する施設であり、施設内でこれらの者を集団として管理するにあたっては内部における規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要があるから・・・この面からその者の【B】的自由及びその他行為の自由に一定の制限が加えられることはやむをえない・・・被拘禁者の新聞・図書等閲覧の自由を制限する場合・・・具体的事情の下でその閲覧を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の【E】性があると認められることが必要であり、かつ・・・制限の程度は障害発生の防止のために必要かつ【C】的な範囲にとどまるべきものと解する
1 A居住 B身体 C合理 D隔離 E蓋然
2 A活動 B身体 C蓋然 D遮断 E合理
3 A居住 B日常 C合理 D遮断 E蓋然
4 A活動 B日常 C蓋然 D隔離 E合理
5 A居住 B身体 C合理 D遮断 E蓋然