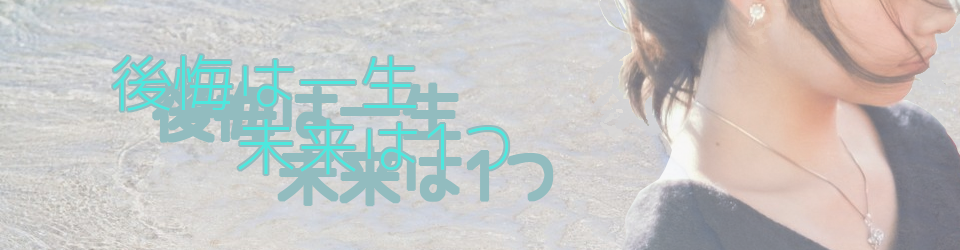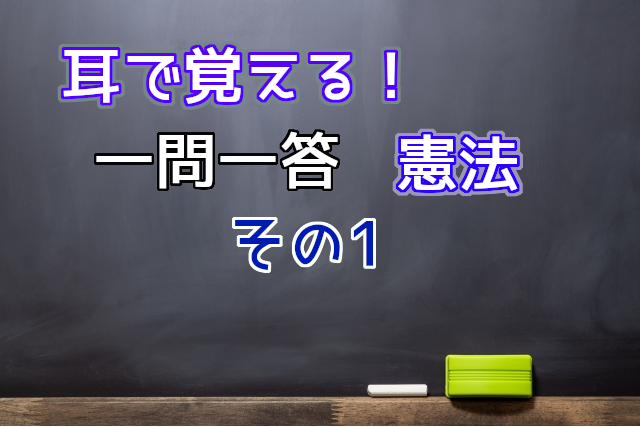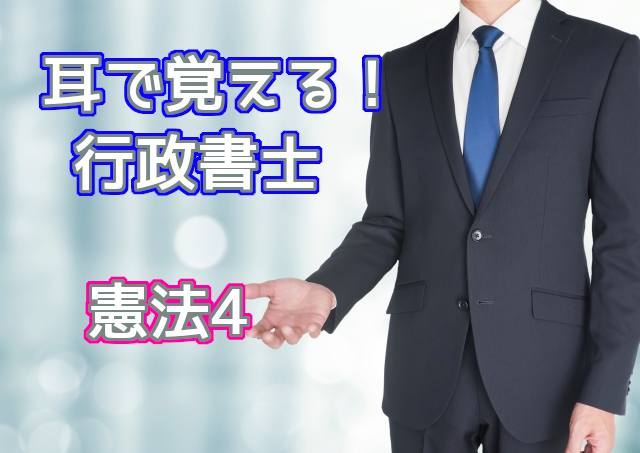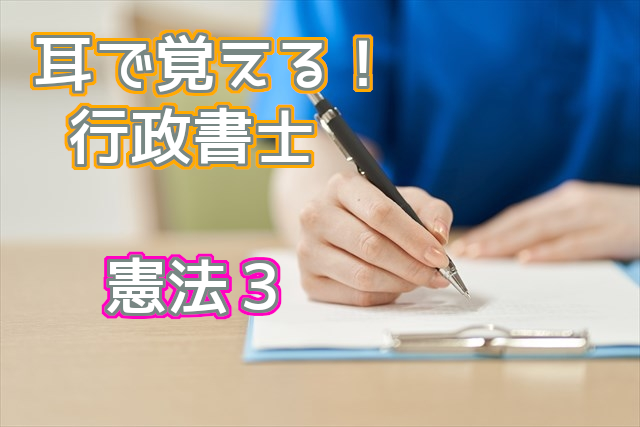
議員の地位に関して妥当なものはどれ
1 衆参両議院の比例代表選出議員に欠員が出た場合、当選順位に従い繰上補充が行われるが、名簿登載者のうち除名・離党その他事由により名簿届出政党等に所属するものでなくなった旨の届出がなされているものは繰上補充の対象とならない
2 両議院の議員は国会の会期中逮捕されないとの不逮捕特権が認められ、憲法が定めるところより、院外における現行犯の場合でも逮捕されない
3 両議院には憲法上自律権が認められており、所属議員への処罰については司法審査が及ばないが、徐名処分については一般市民法秩序と関連するため、裁判所は審査を行うことが出来る
4 地方議会の自律権は議員の自律権とは異なり法律上みとめられたものにすぎないので、裁判所は除名に限らず地方議会による議員への懲罰について広く審査を行うことが出来る
5 地方議会の議員は住民から直接選挙されるので国家議員同様に免責特権が認められ、議会で行った演説・討論または表決について議会外で責任を問われない
家族・婚姻に関して妥当なものはどれ
1 嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の1/2とする民法規定は、当該規定が補充的に機能する規定であることから本来は立法裁量が広く認められる事柄であるが、法律婚の保護という立法目的に照らすと著しく不合理であり憲法に違反する
2 国籍法が血統主義を採用する事には合理性があるが、日本国民との法律上の親子関係の存否に加え、日本との密接な結びつきの指標として一定の要件を設けこれを満たす場合に限り出生後の国籍取得を認めるとする立法目的には、合理的な根拠がない為不合理な差別に当たる
3 出生届に嫡出子または嫡出でない子の別を記載すべきものとする戸籍法の規定は、嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取り扱いを定めたものであり憲法に違反する
4 厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間(100日)を超えて女性の再婚を禁止する民法の規定は婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超え憲法に違反するに至った
5 夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占める状況は実質的に法の下の平等に違反する状態といいうるが、婚姻前の氏の通称使用が広く定着していることからすると直ちに違憲とまでは言えない
選挙権・選挙制度に関して妥当でないものはどれ
1 国民の選挙権それ自体を制限することは原則許されず、制約が正当化されるためにはやむを得ない事由がなければならないが、選挙権を行使する為の条件は立法府が選択する選挙制度によって具体化されるものであるから、選挙権行使の制約をめぐっては国会の広い裁量が認められる
2 立候補の自由は選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持するうえできわめて重要な基本的人権であることに鑑みれば、これに対する制約は特に慎重でなければならない
3 一定の要件を満たした政党にも選挙運動を認める事が是認される以上、そうした政党に所属する候補者とそれ以外の候補者との間に選挙運動上の差異が生じても、それが一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達している場合にはじめて国会の裁量の範囲を逸脱し、平等原則に違反する事になる
4 小選挙区制は、死票を多く生む可能性のある制度であることは否定しがたいが、死票はいかなる制度でも生ずるものであり、特定の政党のみを優遇する制度とは言えないのであって、選挙を通じて国民の総意を議席に反映させる一つの合理的方法といえる
5 比例代表選挙において選挙人が政党等を選択して投票し、各政党等の得票数の多寡に応じて、政党等があらかじめ定めた当該名簿の順位に従って当選人を決定する方式は、投票結果すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点で選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異ならず直接選挙といえる
教科書検定制度の合憲性に関して妥当でないのはどれ
1 国は広く適切な教育政策を樹立・実施すべき者として、また子ども自身の利益を擁護し、子供の成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当な範囲で教育内容についてもこれを決定する権能を有する
2 教科書検定による不合格処分は、発表前の審査によって一般図書としての発行を制限する為、表現の自由の事前抑制に該当するが、思想内容の禁止が目的ではないから検閲には当たらず、憲法21条2項前段の規律に違反するものではない
3 教育の中立・公正、教育水準の確保などを実現するための必要性、教科書という特殊な形態での発行を禁ずるにすぎないという制限の程度などを考慮すると、ここでの表現の自由の制限は合理的で必要やむを得ない限度のものというべきである
4 教科書は学術研究の結果の発表を目的とするのではなく、検定制度は一定の場合に教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから、学問の自由を保障した憲法23条の規定に違反しない
5 行政処分には憲法31条による法定手続の保障が及ぶと解すべき場合があるとしても、行政手続きは行政目的に応じて多種多様であるから、常に必ず行政処分の相手方に告知・弁解・防禦の機会を与える必要はなく、教科書検定の手続は憲法31条に違反しない
動物愛護や自然保護に強い関心を持つ裁判官Aは毛皮の採取を目的とした野生動物の乱獲を批判する為、休日に仲間と派手なボディペインティングをした風体でデモ行進を行いその写真をSNSに掲載した所、賛否両論の社会的反響を呼ぶことになった。事態を重く見た裁判所はA氏に懲戒手続を開始した。
このニュースに関心をもったBさんは事件の今後の成り行きを予測する為情報集を試みたところ、裁判官の懲戒手続一般についてネット上で1~5の出所不明な情報を発見した。このうち妥当なのはどれか
1 裁判官の身分保障を手続的に確保する為罷免については国会に設置された弾劾裁判所が、懲戒については独立の懲戒委員会が決定を行う
2 裁判官の懲戒内容は、職務停止・減給・戒告・過料とされる
3 司法権を行使する裁判官に対する政治運動禁止の要請は一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請よりも強い
4 政治運動を理由とした懲戒が憲法21条に違反するか否かは、当該政治運動の目的や効果、裁判官の関わり合いの程度の3点から判断されなければならない
5 表現の自由の重要性に鑑みれば、裁判官の品位を辱める行状があったと認定される事例は著しく品位に反する場合のみに限定されなければならない
学問の自由に関して妥当でないのはどれ
1 学問研究を使命とする人や施設による研究は真理探究のためのものであるとの推定が働くと学説上考えられてきた
2 先端科学技術をめぐる研究は、その特性上一定の制約に服する場合もあるが、学問の自由の一環である点に留意して、日本では罰則によって特定の種類の研究活動を規制することまではしていない
3 判例によれば、大学の学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである
4 判例によれば学生の集会が実社会の政治的社会活動に当たる行為をする場合には大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない
5 判例によれば普通教育において児童生徒の教育に当たる教師にも教授の自由が一定の範囲で保障されるとしても完全な教授の自由を認めることは到底許されない
生存権に関して妥当なのはどれ
1 憲法が保障する「健康で文化的な最低限の生活」を営む権利のうち「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが、「健康で文化的な生活」は抽象度の高い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる
2 行政府が現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し法律によって与えられた裁量権の限界を超えた場合または裁量権を濫用した場合には違法な行為として司法審査の対象となり得る
3 憲法25条2項は、社会的立法および社会的施設の創造拡充により個々の国民の生活権を充実すべき国の一般的債務を、同条1項は国が個々の国民に対しそうした生活権を実現すべき具体的義務を負っている事それぞれ定めたものと解される
4 現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の侵害が問題となることから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである
5 生活保護の支給額が「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである
デモクラシーの刷新を綱領に掲げる政党Xは衆議院議員選挙の際の選挙公約として以下の公職選挙法改正を提案した。このうち憲法上議論となり得ないのは1~5のどれ
ア 有権者の投票を容易にするため、自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票する事もでき、身近な人々の間での政治的な議論が活性化する事が期待される
イ 有権者の投票率を高める為、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとともに、それでも3回続けて棄権した有権者には罰則を科す
ウ 過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める
エ 地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり国会で地方の立場を主張できるようにする
1 普通選挙
2 直接選挙
3 自由選挙
4 平等選挙
5 秘密選挙
百里基地訴訟で□にあてはまる文章で妥当なものはどれ
憲法九八条一項は憲法が国の最高法規であること、すなわち憲法が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有し憲法に違反するその余の法形式の全部または一部はその違反する限度において法規範としての本来の効力を有しないことを定めた規定であるから、同条項にいう「国務に関するその他の行為」とは同条項に列挙された法律・命令・詔勅と同一の性質を有する国の行為を意味し、従って行政力を行使して法規範を定立する国の行為であるから、かかる法規範を定立する限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきであるが、国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は右のような法規範の定立を伴わないから憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないものと解するべきである。・・・原審の適法に確定した事実関係の下では、本件売買契約は、□
1 国が行った行為であって私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とはいえず、右のような法規範の定立を伴うことが明らかであるから憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである
2 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、行政目的のために選択された行政手段の一つであり、国の行為と同視さるべき行為であるから憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである
3 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、そこにおける法規範の定立が社会法的修正を受けていることを考慮すると、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである
4 国が行った法規範の定立ではあるが、一見極めて明白に違憲とは到底言えないため、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである
5 国が行った行為ではあるが私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである
空欄に当てはまる語句の組み合わせで妥当なものはどれ
大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除及び復権は[ア]においてこれを決定し・・・[イ]はこれを[ウ]することにした。ここにあげた[エ]権は旧憲法では[イ]の[オ]に属していたが、新憲法においてその決定はこれを[ア]の権能とし、[イ]はただこれを[ウ]するに止まる事になったのであるが、議会における審議に当って、[エ]は法の一般性又は裁判の法律に対する忠実性から生ずる不当な結果を調整する作用であり、立法権・司法権及び行政権の機械的分立から生ずる不合理を是正するための制度であってその運用には政治的批判を伴うものであることを理由として、その実質的責任はすべてこれを[ア]に集中するとともに、「それが国民にもたらす有難さを[ウ]の形式を以て表明する」こととしたと説明している
1 ア 最高裁判所 イ 国会 ウ 議決 エ 免訴 オ 自律権
2 ア 内閣 イ 天皇 ウ 認証 エ 恩赦 オ 大権
3 ア 内閣 イ 天皇 ウ 裁可 エ 免訴 オ 専権
4 ア 内閣総理大臣 イ 内閣 ウ 閣議決定 エ 恩赦 オ 専権
5 ア 国会 イ 天皇 ウ 認証 エ 恩赦 オ 大権