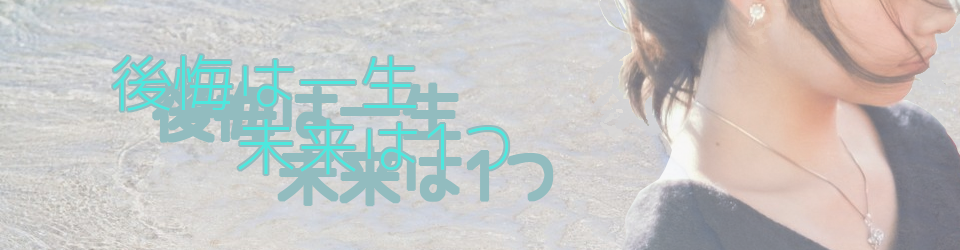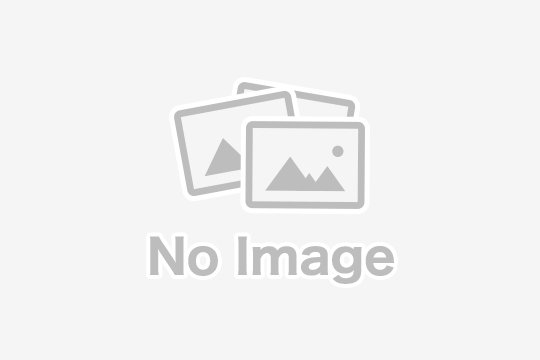いかなる行為が犯罪となり、それに対していかなる刑罰が科せられるかについて、あらかじめ「成文の法律」をもって規定しておかなければならない原則を【A】という。
憲法31条は、手続法さえ法定されていればよいというものではなく、刑事手続きにおいて適用されるべき【B】もまた事前に法定されていなければならないと解されている。
犯罪に対して科すべき刑種又は刑量を全く定めない刑を規定することを【A】という。刑期の長短が執行者の恣意に委ねられてしまい、罪刑を法定したことが無意味になるため、罪刑法定主義に反して【B 許される or 許されない】
刑の長期、短期を定めて言い渡し、その範囲内で現実の執行期間を裁量に委ねる【C】は必ずしも罪刑法定主義に反しない
【A】とは、法律に規定のない事項に対し、これと類似する性質を有する事項に関する法規を適用する事。法律が規定している事項を超えて法律が規定していない事項まで法律を適用させるものになるため、解釈によっては【B】を無意味にする危険があるので、【C】に反して許されない。
ただし、被告人に有利に【A】をするのは許される。(【C】は被告人の人権を保護する原則だからである)
何人も、実行時に適法であった行為は、刑事上責任を問われない。これを【A】の原則という。
これを認めると【B】を害し、個人の自由を不当に【C】するからである。
明確性の原則とは、刑罰法規はできるだけ【A】であり、かつ、その意味するところが【B】でなければならず、刑罰法規の内容があいまい不明確のため通常の判断能力を有する【C】の理解において識別できない場合、罪刑法定主義に反し、そのような刑罰法規が【D】となるとする原則。
日本国内に犯罪地がある場合に刑法を適用する事を【A】という。
【B】の全部又は一部が日本国内で発生した場合に犯罪地が日本国内にあるとあれる。日本国内とは日本の【C】【D】【E】内の事。国外の【F】内や【G】内も日本国内に準ずる。
日本国内で教唆・幇助が行われれば、正犯行為が国外で行われても【A】【B】につき刑法が適用されるが、【C】は刑法が適用されない。
教唆・幇助が国外で行われた場合、【C】行為が日本国内で行われれば【A】【B】につき刑法が適用される。
属人主義とは、【A】が【B】において、一定の重大な罪を犯した場合に刑法を適用すること。
刑法第3条の2 この法律は【B】において、【A】に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
第176条 【C】 第177条 【D】 第178条 1.2 【E】第179条 1.2 【F】 第180条 【G】 第181条 【H】
第199条 【I】
第204条 【J】及び(205条傷害致死)
第220条 【K】 第221条 【L】
第224条 【M】 第225条 【N】(225条の2 身代金目的略取等)
第226条 【O】(226条の2 人身売買) 第227条 【P】 第228条 【Q】
第236条 【R】 第238条 【S】 第239条 【T】 第240条 【U】
第241条 【V】
「犯罪後」とは【A】を意味する。
結果犯・結果的加重犯においても、結果が発生した時ではなく【B】が基準となる
刑は【A】【B】【C】【D】【E】及び【F】を主刑とし、【G】を付加刑とする。
主刑とは、判決においてそれだけ【E】して言い渡すことができる刑罰。
付加刑とは、主刑が言い渡される場合に限り、これに【F】して言い渡す事のできる刑罰。
受刑者の生命を剥奪する刑罰を【A】といい、【B】がある。
受刑者の自由を剥奪する刑罰を【C】といい、【D】【E】【F】がある。
受刑者から一定額の財産を剥奪する刑罰を【G】といい、【H】【I】【J】がある。
懲役は無期及び有期とし、有期懲役は【A】以上【B】以下とする。
懲役は刑事施設に拘置して【C】を行わせる。
禁錮は 無期及び有期とし、有期禁錮は【A】以上【B】以下とする。
禁錮は刑事施設に拘置する。
死刑又は無期懲役若しくは禁錮を減軽して有期懲役又は禁錮とする場合は、その長期を【D】とする。
有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては【D】にまで上げることができ、これを減軽する場合においては【E】に下げることができる。
罰金は【A】以上とする。これを減軽する場合においては【A】未満に下げることができる。
拘留は【B】以上、【C】未満とし、【D】に拘置する。
科料は【E】以上【A】未満とする
罰金を完納することができない者は【1】の期間、【A】に留置する。
科料を完納することができない者は【2】の期間、【A】に留置する。
罰金を併科した場合又は罰金と科料を併科した場合における留置期間は【B】を超えることができない。
科料を併科した場合における留置期間は【C】を超えることができない。
【D】については、裁判が確定した後【E】以内、【F】については裁判が確定した後【G】以内は、本人の承諾がなければ【H】をすることができない。
没収することができるものは、「犯罪行為を【A】」、「犯罪行為の【B1又はB2】」、「犯罪行為によって生じ、若しくは【C】又は犯罪行為の【D】」、「これらの物の対価として得た物」。
没収は【E】に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、【E】に属する物であっても、犯罪の後にその者が【F】ものであるときは没収することができる。
没収とは、犯罪に関する一定の【A1】の【A2】を剥奪して【B】処分の事。
【C1・C2】:主として犯罪予防を目的として没収される。
【D1・D2・D3・D4】:犯罪の不正利益を犯罪者の手元に残さないことを目的として没収される。
犯罪組成物件とは、【A】の要素となっている物で、賄賂提供罪の提供物など。
犯罪供用物件とは、犯罪行為の【B1】又は【B2】とした物で、殺人に使用された凶器など。
犯罪【C】物件とは、犯罪行為によって存在するに至った物で、文書偽造における偽造文書など。
犯罪【D】物件とは、犯罪行為によって得た物で、賭博によって得た金銭など。
犯罪【E】物件とは、犯罪行為の【E】として得た物で、殺人幇助の謝礼など。
【F】物件とは、 犯罪【C】物件 ・ 犯罪【D】物件 ・ 犯罪【E】物件 の【F】として得た物で、窃取した現金で購入した物など。
【A】とは、没収可能であったものが、【B】で事実上又は法律上没収できなくなっている場合に、その物に代わるべき【C】の納付を命ずる【D】処分のこと。
追徴できるのは、犯罪【A】物件、 犯罪【B】物件 、 犯罪【C】物件 、【D】物件 であって、 犯罪【E】物件、 犯罪【F】物件 は追徴が出来ない。
刑期は裁判が【A】日から起算する。拘禁されていない日数は裁判確定後であっても刑期に算入しない。
受刑の初日は時間にかかわらず【B】として計算する。時効期間の初日も同様とする。
刑期が終了した場合の釈放は、その終了の日の【C】に行う。
次に掲げる者が、【A1】年以下の懲役若しくは禁錮又は【A2】以下の罰金の言渡しを受けた時、情状により、裁判が確定した日から【B1】以上【B2】以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
〇前に【C】の刑に処せられたことがない者
〇前に【C】の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から【D】以内に【C】の刑に処せられたことがないもの。
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の【A】を、無期刑については【B】を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる
【A】とは、確定裁判を経ていない2個以上の罪のこと。
【A】のうちの1個の罪について【B】に処するときは他の刑を科さない。ただし没収はこの限りではない。
【A】のうちの1個の罪について 【C1】又は【C2】に処するときも他の刑を科さない。ただし、【D1】【D2】及び没収はこの限りではない。
併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその【A】を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の【B】を超える事は出来ない。
併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の【A】以下で処断する。
併合罪について2個以上の裁判があったときはその刑を併せて執行する。ただし、【B】を執行すべきときは、没収を除き他の刑を執行せず、【C1又はC2】を執行すべき時は罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。