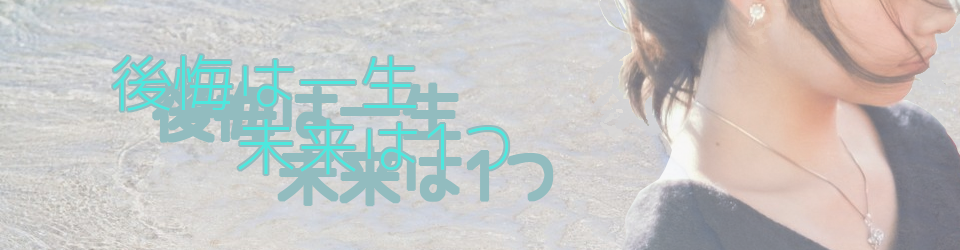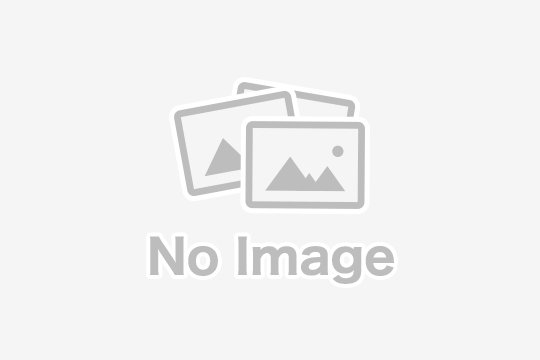法人事業主は、その従業者が法人の業務に関して行った犯罪行為について、両罰規定が定められている場合には、選任監督上の過失がなくても刑事責任を負う
法人事業主を両罰規定により処罰するためには、現実に犯罪行為を行った従業者も処罰されなければならない
法人事業主が処罰される場合には、その代表者も処罰される
刑法各則に規定された行為の主体には、法人は含まれない
刑法各則に規定された行為の客体には、法人は含まれない
両罰規定に関し、「見解」A説ないしC説に従って、後記「罰則」の適用に関する後記1から5までの「記述」を検討し誤りを2つ選べ
「見解」
A説:両罰規定は,法人が無過失であっても代表者や従業者の責任が法人に転嫁されることを政策的に認めたものである。
B説:法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり,法人の従業者の違反行為については、法人の代表者の当該従業者に対する選任監督上の過失が推定され、過失責任に基づき法人が
処罰される。
C説:法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり,法人の従業者の違反行為については、法人の代表者の当該従業者に対する選任監督上の過失が擬制され,過失責任に基づき法人が処罰される。
「罰則」
出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項
次の各号のいずれかに該当する者は 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し , ,又はこれを併科する。
一 事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた者
同法第76条の2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して第73条の2(中略)の罪(中略)を犯したときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。
「記述」
1.A説によれば,甲社代表取締役乙が,自社の事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた場合 甲社に出入国管理及び難民認定法違反の罪 同法第73条の2第1項 第76条の2 , ( ,,以下「不法就労助長罪」という )が成立する。
2.A説によれば,甲社従業者丙が,自社の事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた場合,甲社に不法就労助長罪が成立する。
3.B説によれば,甲社代表取締役乙が,自社の事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた場合,甲社の乙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り,甲社に不法就労助長罪が成立する。
4.B説によれば,甲社従業者丙が,自社の事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた場合,甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り,甲社に不法就労助長罪が成立する。
5.C説によれば,甲社従業者丙が,自社の事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた場合,甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り,甲社に不法就労助長罪が成立する
不作為犯は、結果発生を防止しなければならない義務が法律上の規定に基づくものでない場合であっても、成立する余地がある。
不作為犯は,死体遺棄罪についても成立する余地がある。
不真正不作為犯の故意は,結果の発生を意欲していなくても,認められる余地がある。
不作為犯は,作為可能性がない場合であっても,成立する余地がある。
不作為犯の因果関係は,期待された作為に出ていれば結果が発生しなかったことが,合理的な疑いを超える程度に確実であったといえない場合であっても,その可能性さえあれば,認められる余地がある。
不真正不作為犯の作為義務は,法律上の規定に基づかなければならない
不真正不作為犯が成立するために,作為可能性を必要としない場合もある
不真正不作為犯の因果関係が認められるためには,期待された作為をしていれば結果が発生しなかったことが,合理的な疑いを超える程度に確実であったことが必要である。
不真正不作為犯は,殺人罪や放火罪については成立するが,財産犯については成立しない。
不作為による放火罪が成立するためには,既発の火力を利用する意思は必ずしも必要ではない。
学生A,B及びCは,不真正不作為犯の作為義務違反に関して次の【会話】のとおり検討している。【会話】中の①から⑤までの( )内から適切な語句を選んだ場合,正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。【会話】中の「法律上の防止義務」とは,法令,法律行為,条理等に基づき法益侵害を防止する法的義務をいい,また,いずれの事例も結果回避は容易であったとする。
「会話」
学生A.「甲は,人通りの多い市街地で自動車を運転していた際,誤って乙を跳ねて重傷を負わせたが,怖くなったことから,乙を放置したまま逃走したところ,乙が死亡した。」という事例において,殺人罪の成否に関し,不真正不作為犯の作為義務を検討してみよう。
私は,不真正不作為犯の作為義務違反は,法律上の防止義務を負う者が,法益侵害への因果関係を具体的・現実的に支配している状況下で防止措置を採らなかった場合に認められると考えるので,甲には作為義務違反が1(a.認められる・b.認められない)ことになる。
学生B.私は,不真正不作為犯の作為義務違反は,法律上の防止義務を負う者が,既に発生している法益侵害の危険を利用する意思で防止措置を採らなかった場合に認められると考えるので,この事例では,甲には作為義務違反が2(a.認められる・b.認められない)ことになる。
学生C.私は,不真正不作為犯の作為義務違反は,法益侵害に向かう因果の流れを自ら設定した者が,その法益侵害の防止措置を採らなかった場合に認められると考えるので,この事例では,甲には作為義務違反が3(a.認められる・b.認められない)ことになる。
学生A.次に,「一人暮らしをしている丙は,自宅に遊びに来ていた丁が帰った後,丁のたばこの火の不始末でカーテンが燃えているのに気付いたが,家に掛けてある火災保険の保険金を手に入れようと考え,そのまま放置して外出したところ,カーテンの火が燃え移って家が全焼した。」という事例において,
非現住建造物等放火罪の成否に関し,不真正不作為犯の作為義務を検討してみよう。C君の立場からだと,丙には作為義務違反が4(a.認められる・b.認められない)ことになるよね。学生B.先ほど話した私の立場からは,今の事例では,丙には作為義務違反が5(a.認められる・b.認められない)ことになる。
次の【事例】及び【判旨】に関する後記1から5までの各【記述】のうち,正しいものはどれ
【事 例】
甲は,手の平で患部をたたいてエネルギーを患者に通すことにより自己治癒力を高めるとの独自の治療を施す特別の能力を有すると称していたが,その能力を信奉していたAから,脳内出血を発症した親族Bの治療を頼まれ,意識障害があり継続的な点滴等の入院治療が必要な状態にあったBを入院中の病院から遠く離れた甲の寄宿先ホテルの部屋に連れてくるようAに指示した上,実際に連れてこられたBの様子を見て,そのままでは死亡する危険があることを認識しながら,上記独自の治療を施すにとどまり,点滴や痰の除去等Bの生命維持に必要な医療措置を受けさせないままBを約1日間放置した結果,Bを痰による気道閉塞に基づく窒息により死亡させた。
【判 旨】
甲は,自己の責めに帰すべき事由によりBの生命に具体的な危険を生じさせた上,Bが運び込まれたホテルにおいて,甲を信奉するAから,重篤な状態にあったBに対する手当てを全面的に委ねられた立場にあったものと認められる。その際,甲は,Bの重篤な状態を認識し,これを自らが救命できるとする根拠はなかったのであるから,直ちにBの生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていたものというべきである。それにもかかわらず,未必的な殺意をもって,上記医療措置を受けさせないまま放置してBを死亡させた甲には,不作為による殺人罪が成立する。
1.Aが甲に対してその特別の能力に基づく治療を行うことを真摯に求めていたという事情があれば,甲にはその治療を行うことについてのみ作為義務が認められるから,この判旨の立場からも殺人罪の成立は否定される。
2.判旨の立場によれば,この事例で甲に患者に対する未必的な殺意が認められなければ,重過失致死罪が成立するにとどまる。
3.判旨は,不作為犯が成立するためには,作為義務違反に加え,既発の状態を積極的に利用する意図が必要であると考えている。
4.判旨は,Aが甲の指示を受けてBを病院から搬出した時点で,甲に殺人罪の実行の着手を認めたものと解される。
5.判旨は,先行行為についての甲の帰責性と甲による引受行為の存在を根拠に,甲のBに対する殺人罪の作為義務を認めたものと解される。
真正不作為犯と不真正不作為犯との違いは,刑罰法規そのものが構成要件要素として明文で不作為を規定しているか否かにある。
作為義務を不真正不作為犯の成立要件とすることにより,結果の発生を回避し得る作為をしなかった複数の者の中から不作為犯の主体となり得ない者を除外することができる。
不作為とは「一定の作為をしないこと」を意味するから,他人の住居内で居住者から退去要求を受けた場合になすべき「一定の作為」が「住居から退去すること」だとすると,「その住居内に居座ること」も「その住居内で財物を窃取すること」も不作為である。
不真正不作為犯を認める見解に対しては,「無から有は生じない」から因果関係が認められないという批判があり得るが,期待された作為を行っていたら結果の発生が避けられたであろうという場合には因果関係が認められるとの反論が可能である。
不真正不作為犯の成立要件としての作為義務を認めるためには不作為者が結果発生の原因となる先行行為を行えば足りるとする見解に対しては,故意又は過失によって人に傷害を与えた者が,その後殺意をもってその人を救助せずに放置して死亡させた事案において,不作為による殺人罪が認められる範囲が狭くなり過ぎるとの批判が可能である。
甲は,Xが管理する工事現場に保管されている同人所有の機械を,同人に成り済まして,甲をXであると誤信した中古機械買取業者Yに売却し,同人に同機械を同所から搬出させた。この場合,甲に,Xに対する窃盗罪の間接正犯が成立する
甲は,追死する意思がないのにあるように装い,その旨誤信したXに心中を決意させた上で毒物を渡し,それを飲み込ませて死亡させた。この場合,甲に,Xに対する殺人罪は成立しない。
甲は,Xに対し,暴行や脅迫を用いて,自殺するように執拗に要求し,要求に応じて崖から海に飛び込んで自殺するしかないとの精神状態に陥らせた上で,Xを崖から海に飛び込ませて死亡させた。この場合,甲に,Xに対する殺人罪は成立しない
甲は,日頃から暴行を加えて自己の意のままに従わせて万引きをさせていた満12歳の実子Xに対し,これまでと同様に万引きを命じて実行させた。この場合,Xが是非善悪の判断能力を有する者であれば,甲に,窃盗罪の間接正犯は成立せず,Xとの間で同罪の共同正犯が成立する。
甲は,財物を奪取するために,当該財物の占有者Xに対し,反抗を抑圧するに足りる程度の暴行や脅迫を用いて,当該財物を差し出すしかないとの精神状態に陥らせた上で,当該財物を差し出させた。この場合,甲に,Xに対する強盗罪は成立せず窃盗罪の間接正犯が成立する
問29~33は、間接正犯が成立するかどうかを答える問題です
甲は,是非弁別能力を有する12歳の長男乙に対し,強盗の犯行方法を教示し、その際に使う凶器を提供して強盗を実行するよう指示したが,その指示は乙の意思を抑圧するものではなく,乙は,自らの意思により強盗の犯行を決意し,甲から提供された凶器を使って,状況によって臨機応変に対処して強盗を実行した。(強盗罪)
医師ではない甲は,妊婦乙からの依頼を受けて乙への堕胎手術を開始したが、その最中に乙の生命が危険な状態に陥ったため,医師丙に依頼し,胎児を乙の母体外に排出させた。(同意堕胎罪)
公務員ではない甲は,公証人乙に対して虚偽の申立てをし,事情を知らない乙をして,公文書である公正証書の原本に虚偽の記載をさせた。(虚偽公文書作成罪)
甲は,乙所有の建材を自己の所有物であると偽って,事情を知らない丙に売却し,丙をして,乙の建材置場から当該建材を搬出させた。(窃盗罪)
間接正犯の成立要件
間接正犯の成立要件は、【A】しながら特定の犯罪を【B】があること、被利用者の行為をあたかも【C】していることである。
相当因果関係説の相当性の判断
次の各【見解】と後記の各【事例】を前提として,後記アからエまでの各【記述】を検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい
【見解】
A.行為当時,客観的に存在した全ての事情及び行為後に生じた事情のうち一般人が予見できた事情を判断の基礎とし,その行為から結果が発生することが相当であると認められる場合に因果関係を肯定する。
B.一般人が認識・予見できたであろう事情及び行為者が認識・予見していた事情を判断の基礎とし,その行為から結果が発生することが相当であると認められる場合に因果関係を肯定する。
C.行為の危険性が結果へと現実化したといえる場合に因果関係を肯定する。行為の危険性は行為時に存在した全ての事情を基礎として判断する。
【事例】
Ⅰ.甲は,乙の顔面を手拳で1回殴打した。その殴打は,それだけで一般に人を死亡させるほどの強さではなかったが,乙はもともと特殊な病気により脳組織が脆弱となっており,その1回の殴打で脳組織が崩壊し,その結果,乙が死亡した。
Ⅱ.甲は,乙の首をナイフで突き刺し,直ちに治療しなければ数時間のうちに死亡するほどの出血を来す傷害を負わせた。乙は,直ちに病院で適切な医療処置を受け,一旦容体が安定したが,その後,医師の指示に従わず安静に努めなかったため,治療の効果が減殺され,前記傷害に基づき死亡した。
Ⅲ.甲は,路上で乙の頭部を激しく殴打し,直ちに治療しなければ1日後には死亡するほどの脳出血を伴う傷害を負わせ,倒れたまま動けない乙を残して立ち去った。そこへたまたま通り掛かった無関係の通行人が,乙の腹部を多数回蹴って,内臓を破裂させ,数時間後に乙は内臓破裂により死亡した。
【記述】
甲の行為と乙の死亡との間の因果関係については,
ア.Ⅰの事例で,行為当時,乙は特殊な病気により脳組織が脆弱となっていることを一般人は認識できず,甲も認識していなかった場合,A及びCの見解からは肯定され,Bの見解からは否定される。
イ.Ⅰの事例で,行為当時,乙は特殊な病気により脳組織が脆弱となっていることを一般人は認識できず,甲も認識していなかったが,甲はこれを認識できた場合,AからCまでのいずれの見解からも肯定される。
ウ.Ⅱの事例で,行為当時,乙が治療を受けた後,医師の指示に従わず安静に努めなくなることを一般人は予見できなかったが,甲は予見していた場合,Bの見解からは肯定され,A及びCの見解からは否定される。
エ.Ⅲの事例で,行為当時,乙が通行人に蹴られることを一般人は予見できず,甲も予見していなかった場合,AからCまでのいずれの見解からも否定される。
判例の立場から正しいか誤りか検討せよ
甲は,他の共犯者5名と共に,約3時間にわたりマンションの一室において,Vの頭部,腹部等を木刀で多数回殴打していたところ,これにより極度の恐怖感を抱いたVが,同室から逃走し,甲らによる追跡から逃れるために,同マンション付近にある高速道路に進入し,疾走してきた自動車に衝突され,死亡した。この場合,甲らの上記殴打行為とVの死亡との間に,因果関係はない
判例の立場から正しいか誤りか検討せよ
甲は,Vの頸部を包丁で刺突し,致命傷になり得る頸部刺創の傷害をVに負わせたところ,Vは,病院で緊急手術を受けたため一命をとりとめ,引き続き安静な状態で治療を継続すれば数週間で退院することが可能となったが,安静にせず,病室内を歩き回ったことから治療の効果が上がらず,同頸部刺創に基づく血液循環障害による肝機能障害により死亡した。この場合,甲の上記刺突行為とVの死亡との間に,因果関係はない。
判例の立場から正しいか誤りか検討せよ
甲は,Vの顔面を1回足で蹴ったところ,特殊な病気により脆弱となっていたVの脳組織が崩壊してVが死亡したが,当該病気の存在について,一般人は認識することができず,甲も認識していなかった。この場合,甲の上記足蹴り行為とVの死亡との間に,因果関係はない
判例の立場から正しいか誤りか検討せよ
甲は,医師資格のない柔道整復師であるところ,自己に全幅の信頼を寄せるVから,風邪の治療について相談を持ち掛けられた際に,Vに対し,食事や水分補給を控える一方,発汗を促すという医学的に明らかに誤った治療法を繰り返して指示し,これに忠実に従ったVが症状を悪化させ,脱水症状に陥り,死亡した。この場合,甲の上記指示行為とVの死亡との間に,因果関係はない。
判例の立場から正しいか誤りか検討せよ
甲は,自動車を運転中,路上で過失により通行人Vに同車を衝突させてVを同車の屋根に跳ね上げ,意識を喪失したVに気付かないまま,同車の運転を続けていたところ,同乗者がVに気付き,走行中の同車の屋根からVを引きずり降ろして路上に転落させ,Vは,頭部打撲に基づく脳くも膜下出血により死亡したが,これが同車との衝突の際に生じたものか,路上に転落した際に生じたものかは不明であった。この場合,甲の上記衝突行為とVの死亡との間に,因果関係はない。
「因果関係の判断基準」
行為者に結果を帰責させるためには、【A】の【B】が結果へと現実化したという必要がある。そのため、【A】の【B】が結果へと現実化したといえる場合に因果関係が認められる事になる
そして、行為自体の危険性が結果へと現実化したかどうかは、「行為自体の【C】」、「【D】の異常性の大小」、「介在事情の【E】」を総合的に判断して決すべきである。
錯誤
学生A,B及びCは,事実の錯誤に関して,次の【会話】のとおり検討している。【会話】中の①から⑪までの( )内から適切な語句を選べ
【会 話】
学生A.Xが甲を狙って殺人の故意で拳銃を発射し,甲にかすり傷を負わせ,さらに,その弾丸が偶然に乙に命中して乙を死亡させた事例について考えてみよう。
私は,同一の構成要件の範囲内であれば,故意を阻却しないと考え,故意の個数については,①(a.故意の個数を問題としない・b.故意の個数を問題とし一個の故意を認める)立場を採ります。ですから,私は,事例の場合,故意犯としては乙に対する殺人既遂罪のみが成立すると考えます。
学生B.私は,基本的にはA君と同じ立場ですが,故意の個数について,②(c.故意の個数を問題としない・d.故意の個数を問題とし一個の故意を認める)立場に立ちます。A君の考えだと,③(e.意図した・f.意図しない)複数の客体に既遂の結果が発生した場合,いずれの客体に故意犯を認めるのか不明だからです。
学生C.B君の立場は,④(g.罪刑法定主義・h.責任主義)に反することになりませんか。私は,この原則を尊重し,⑤(i.客体の錯誤・j.方法の錯誤)の場合には故意を認めますが,⑥(k.客体の錯誤・l.方法の錯誤)の場合には故意を認めるべきではないと思います。ですから,私は,事例の場合,乙に対する殺人既遂罪は成立しないと考えます。
学生A.でも,C君の立場では,方法の錯誤と客体の錯誤との明確な区別が可能であることが前となりますね。また,未遂犯や過失犯を処罰する規定の有無によっては,処罰の範囲が不当に⑦(m.狭まる・n.広がる)ことになると思います。一方で,B君の立場では,処断刑が不当に重くなりませんか。
学生B.私は,甲に対する罪と乙に対する罪の関係を⑧(o.併合罪・p.観念的競合)と考えますので,処断刑はA君の立場による場合と同一となります。
学生A.でも,複数の客体に既遂の結果が発生した場合,⑨(q.意図した・r.意図しない)客体についての⑩(s.故意犯・t.過失犯)を,刑を⑪(u.重くする・v.軽くする)方向で量刑上考慮するとなると,やはり問題ではないでしょうか。
規範的構成要件要素の錯誤
故意責任の本質は、【A】を認識して規範に直面したにもかかわらずあえてその犯罪行為に及んだ事に対する【B】非難であり、規範は裁判官等の専門家ではなく一般人に対するものである。
したがって、規範的構成要件要素については、一般人にとって反対動機が形成可能な程度の【C】と【D】があれば足り、【E】な認識は不要というべきである。
具体的事実の錯誤
規範は【A】の形で国民に与えられており、【A】の範囲内で符合している限り【C】があるというべきであるから、【D】と【E】が構成要件の範囲内で符合している限り、故意を阻却しないと解する。
そして、故意犯が複数成立しても、これらは【F】の関係にあって科刑上は1の罪として扱われるから処断上格別の不都合はなく、【G】だけ故意犯が成立すると解する
因果関係の錯誤
故意の関係で重要なのは【A】が存在することであり、その具体的な因果経過は重要ではないことから、既遂犯の故意が認められるためには【B】と【C】だけで足り、【A】の認識は不要である。したがって因果関係の錯誤は故意を【D】しない。
早すぎた構成要件の実現
行為者が第1行為の後に行う第2行為により結果を発生させようとしていたが、第1行為により【A】されてしまった場合に、第1行為につき【B】が認められるかどうかが問題となる
この点について、1、第1行為が第2行為を確実かつ容易に行うために【C】なものであったこと、2、第1行為に成功した場合【D】する上で障害となるような【E】こと、3、第1行為と第2行為との間に【F】があることを考慮し、第1行為を開始した時点ですでに結果が発生する【G】が認められる場合には、第1行為につき実行の着手が認められる
抽象的事実の錯誤
【A】は構成要件の形で【B】に与えられており、【C】限り故意があるというべきであるから、【D】した内容と、【E】が構成要件の範囲内で符合していない場合、故意を【F】するのが原則である
しかし、【D】した事実と【E】の間に実質的な重なり合いが認められる場合、すなわち【G】と【H】が同一である場合には、例外的に故意が認められると解する。
過失
過失を構成要件要素としている犯罪を【A】という。
過失とは注意義務違反のことであり、注意義務とは「【B】義務」と「【C】義務」のことである。そして、これらの義務が課される前提として、結果の【D】と【E】が必要である。
過失相殺の適用により過失の責任を免れる事は出来ない。
過失犯の成立に必要な注意義務は必ずしも【F】があることを要しない
過失犯が成立する為には結果発生の【A】が必要である。
【A】は結果予見義務と結果回避義務を基礎付けるものであるため、【B】が結果回避を【C】があれば足りる。
また、【D】及び結果発生に至る【E】の予見が可能であれば足りる
事例に関する記述で、判例に照らし妥当か妥当でないか。
【事 例】
土木作業員甲及び乙は,現場監督者丙の監督の下で,X川に架かる鉄橋の橋脚を特殊なA鋼材を用いて補強する工事に従事していたが,作業に手間取り,工期が迫ってきたことから,甲及び乙の2人で相談した上で,より短期間で作業を終えることができる強度の弱いB鋼材を用いた補強工事を共同して行った。その結果,工期内に工事を終えることはできたものの,その後発生した豪雨の際,A鋼材ではなくB鋼材を用いたことによる強度不足のために前記橋脚が崩落し,たまたま前記鉄橋上を走行していたV1運転のトラックがX川に転落し,V1が死亡した。なお,甲及び乙は同等の立場にあり,甲及び乙のいずれについても,B鋼材を工事に用いた場合に強度不足のために前記橋脚が崩落することを予見していなかったものの,その予見可能性があったものとする。
ア.甲及び乙には,強度の弱いB鋼材で補強工事を行うことの意思連絡はあるが,不注意の共同はあり得ないから,甲及び乙に業務上過失致死罪の共同正犯が成立する余地はない。
イ.丙は,甲及び乙が強度の弱いB鋼材で補強工事を行っていることを認識していたが,工期が迫っていたことから,これを黙認したという場合,直接行為者である甲及び乙に過失が認められたとしても,更に丙に過失が認められる余地がある。
ウ.仮に,甲及び乙において,V1が死亡するに至る実際の因果経過を具体的に予見することが不可能であった場合,甲及び乙には業務上過失致死罪は成立しない。
共同正犯に関する刑法第60条は,意思の連絡を要件としているので,過失犯には適用されない
重過失とは,重大な結果を惹起する危険のある不注意な行為をすることをいう
過失犯の成立に必要となる結果発生の予見可能性は,内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度の予見の可能性で足りる
ホテルの火災により死傷者が出た場合,火災発生時に現場にいなかったホテル経営者には業務上過失致死傷罪が成立することはない
行為者が法令に違反する行動をした事案においても信頼の原則が適用される場合がある
公道における自動車の運転や、工事現場の共同作業など、他者が【A】をとることを信頼する事が相当といえる場合、たとえ自己と他者の行動が相まって構成要件的結果が発生したとしても、結果回避義務があったとはいえないため、過失犯は成立しない。
信頼の原則には、「他者への信頼が成り立っているといえる【B】」、「他者への【C】」、「他者への【C】が【D】であること」が必要となる
正当防衛 正当行為 緊急避難
構成要件に該当する行為につき違法性の推定を覆して行為を適法なものとする特別の事情のことを【A】という。
刑法は【A】の典型として【B】、【C】、【D】を規定している(違法性の判断は非類型的なものであるから、【A】をこの3つに限定するという趣旨ではない)
正当防衛とは、【A】に対して【B】するためやむを得ずにした行為のこと。
防衛の【C】行為は、情状により、その刑を【D】し、又は【E】することができる。
正当防衛においては【A】が要件とされている。
急迫とは、【B】が現に存在しているか、又は【C】を意味する。
急迫不正の侵害がないのにあると誤信して、防衛の意思で反撃行為を行った場合、正当防衛は成立し得ない。
相手方による侵害を【A】している者が、自己の権利を防衛する為相手方に先んじて加害行為をする事が効果的な状況において、相手方による侵害が【B】前に加害行為をした場合、正当防衛は成立しない。
侵害を予期し、その機会を利用して【A】する意思をもって臨んだ場合は、【B】を認めることはできない。(【C】意思)
反撃行為を行った者が【D】していた場合でも正当防衛は成立しうる。
不正とは【A】であることで、侵害が全体としての【B】に反すること。
侵害とは【C】又は【D】行為のことで、【E】行為、【F】行為いずれでもよく、加害者の【F】行為に対しても正当防衛が成立する。
防衛行為は【A】をもってなされることが必要だが、相手の加害行為に対し憤激又は逆上して反撃を加えても、直ちに【A】を欠くものと解すべきでない。
防衛に名を借りて侵害者にに対し積極的に攻撃を加える行為は、【A】と【B】が併存している場合は【A】の意思を欠くものではないので正当防衛と評価できる
防衛の意思の要件の存否は、不正の侵害に対し【A】時点において問題となり、侵害の急迫性は、防衛行為を正当なものとする前提としての状況なので、その要件の存否は【B】の段階において問題となる。
防衛行為は【C】反撃行為として行われなければならない。そのため、防衛の為の行為が【D】に向けられたときは正当防衛は成立せず、【E】の成否が問題となるに過ぎない
防衛行為は【A】であることを要する。【A】として正当防衛が成立するには、防衛行為が【B】として相当性を有するものであれば足り、防衛行為によって生じた害が【C】の程度を超えた場合でも成立しうる。
相手方を【A】して相手方による侵害を【B】がそれに対し反撃した場合、正当防衛が成立する余地がある。
【A】とは、急迫不正の侵害に対し、防衛の意思で、防衛の【B】を行った場合のことである。
【A】には、防衛行為自体が侵害排除に必要とされる以上の侵害性を有していた場合である【C】と、侵害が終了した後においても、さらに防衛行為を続けた場合である【D】がある。