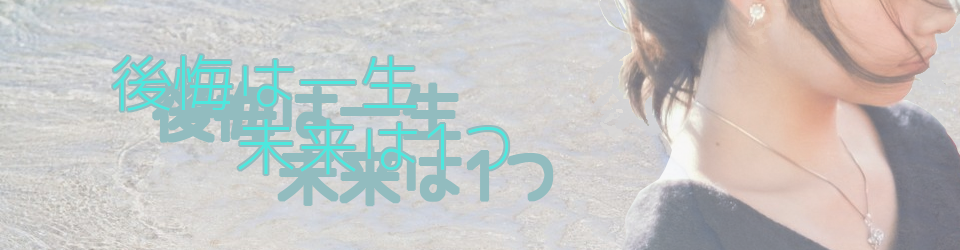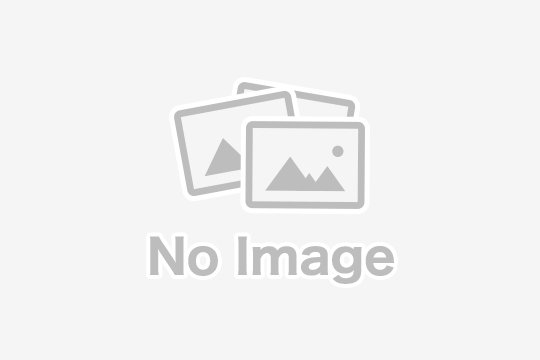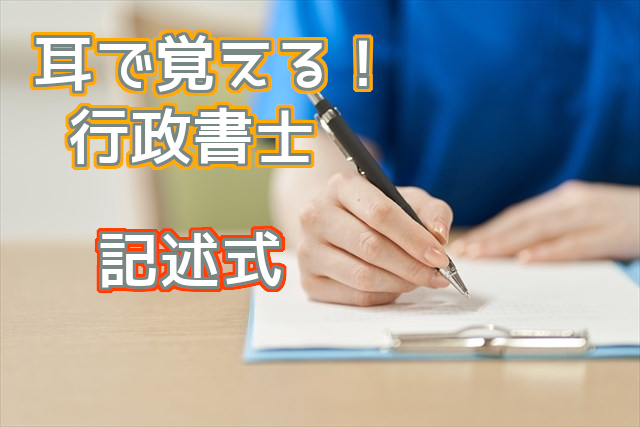
A県内の一定区域において、土地区画整理事業が計画された。それを施行する為、土地区画整理法に基づくA県知事の認可を受けて、土地区画整理組合が設立され、合わせて、本件事業にかかる事業計画も確定された。これを受けて本件事業が施行され、工事完了などを経て、最終的に、本件組合は、換地処分を行った。
Xは、本件事業の区域内の宅地につき所有権を有し、本件組合の組合員である所、本件換地処分は換地の配分につき違法なものであるとして、その取り消しの訴えを提起しようと考えたが、同訴訟の出訴期間がすでに経過していることが判明した。
この時点において、本件換地処分の効力を争い、換地のやり直しを求めるため、Xは誰を被告として、どのような行為を対象とする、どのような訴訟を提起すべきか。
AはBとの間で、A所有の甲土地をBに売却する旨の契約を締結したが、Aが本件契約を締結するに至ったのは、平素からAに恨みを持っているCが、Aに対し甲土地の地中には戦時中に軍隊によって爆弾が埋められており、いつ爆発するかわからないといった嘘の事実を述べたことによる。Aはその爆弾が埋められている事実をBに伝えたうえで、甲土地を時価の1/2程度でBに売却した。売買から1年後に、Cに騙されたことを知ったAは、本件契約に係る意思表示を取り消すことが出来るか。「本件契約に係るAの意思表示」を「契約」と表記して40字程度で記述せよ
【設例】
A所有の甲不動産をBが買い受けたが登記未了であったところ、その事実を知ったCが日頃Bに対して抱いていた怨恨の情を晴らすため、AをそそのかしてもっぱらBを害する目的で甲不動産を二重にCに売却させ、Cは登記を了した後、これをDに転売して移転登記を完了した。BはDに対して甲不動産の取得を主張できるか。
【判例の解説】
上記設例におけるCはいわゆる背信的悪意者に該当するが、判例はかかる背信的悪意者からの転得者Dについて、無権利者からの譲受人ではなくD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、甲不動産の取得をもってBに対抗しうるとされている。
上記の設例について、上記の判例の解説の説明はどのような理由に基づくものか。「背信的悪意者は」に続けて背信的悪意者の意義をふまえつつ、Dへの譲渡人Cが無権利者でない理由を記述せよ
A所有の雑居ビルは、消防法上の防火対象物であるが、非常口が設けられていないなど、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり、危険な状態にある。しかし、その地域を管轄する消防署の署長Yは、Aに対して改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令をすることなく放置している。こうした場合、行政手続法によれば、Yに対してどのような者が、どのような行動をとることができるか。また、これに対してYはどのような対応をとるべきこととされているか。
消防法
第5条1項 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権限を有する関係者に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる
Aは、木造2階建ての別荘一棟(区分所有建物でない)をBら4名と共有しているが、同建物は建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきた。そこで、Aは同建物を建て替えるか、またはいくつかの建物部分を修繕・改良(以下修繕等とよび、解答においても修繕等と記すること)する必要があると考えている。
これらを実施する為には、建て替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か。「建て替えには」に続いて民法の規定に照らし記述せよ。(上記の修繕については民法の定める「変更」や「保存行為」には該当しないものとし、敷地の権利は考慮しないものとする)
Aは自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったため、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。このような契約を何といい、また、この契約に基づきCの上記50万円の代金支払請求権が発生する為には、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。
XはA県B市内において、農地を所有し、その土地において農業を営んできた。しかし、高齢のため農作業が困難となり、後継者もいないため、農地を太陽光発電施設として利用する事を決めた。そのために必要な農地法4条1項所定のA県知事による農地転用許可を得る為、その経由機関とされているB市農業委員会の担当者と相談したところ、「B市内においては太陽光発電の為の農地転用は認められない」として、申請用紙の交付を拒否された。そこでXはインターネットから入手した申請用紙に必要事項を記入してA県知事あての農地転用許可の申請書を作成し、必要な添付書類とともにB市農業委員会に郵送した。ところがこれらの書類は「この申請書は受理できません」とするB市農業委員会の担当者名の通知を添えて返送されてきた。この場合農地転用許可を得る為Xは、いかなる被告に対しどのような訴訟を提起すべきか。
農地法
(農地転用の制限)
第4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可を得なければならない
2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。
3 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があったときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請者に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない
画家Aは、BからAの絵画(本件絵画といい、評価額は500万円~600万円である)を購入したい旨の申し込みがあったため、500万円で売却することにした。ところが、A・B間で同売買契約を締結した時に、Bは成年被後見人であったことが判明したため(成年後見人はCで、その状況は現在も変わらない)、Aは本件契約が維持されるか否かについて懸念していたところ、Dから本件絵画を気に入っているため600万円ですぐにでも購入したい旨の申し込みがあった。Aは本件契約が維持されない場合には本件絵画をDに売却したいと思っている。Aが本件絵画をDに売却する前提として、Aは誰に対し、一か月以上の期間を定めてどのような催告をし、その期間内にどのような結果を得る必要があるか。なお、AおよびDは、制限行為能力者ではない。
「Aは」に続けて記述せよ。記述にあたり「本件契約」を入れることとし、「1か月以上の期間を定めて」および「その期間内に」の記述は省略する事
甲自動車を所有するAは、別の自動車を取得したため、友人であるBに対して甲を贈与する旨を口頭で約し、Bも喜んでこれに合意した。しかしながらAは、しばらくして後悔するようになり、Bとの間で締結した甲に関する贈与契約をなかったことにしたいと考えるに至った。甲の引渡しを求めるBに対し、Aは民法の規定に従い、どのような理由でどのような法的主義をすべきか。なお、この贈与契約において無効及び取消の原因は存在しないものとする
A市は、市内へのパチンコ店の出店を規制する為、同市内のほぼ全域を出店禁止区域とする条例を制定した。しかし、事業者Yはこの条例は国の法令に抵触するなどと主張して、禁止区域内でのパチンコ店の建設に着手した。これに対してA市は、同条例に基づき市長名で建設の中止命令を発したが、これをYが無視して建設を続行している為、A市はYを被告とし、建設の中止を求める訴訟を提起した。最高裁判所の判例によれば、こうした訴訟は、どのような立場でA市が提起したものであるとされ、また、どのような理由でどのような判決がなされるべきことになるか。
AはBに対して100万円の売買代金債権を有していたが、同債権については、A・B間で譲渡禁止特約が付されていた。しかし、Aは特約に違反して上記100万円の売買代金債権をその弁済期経過後にCに対して譲渡し、その後Aが、Bに対しCに譲渡した旨の通知をした。Bはその通知があった後直ちに、Aに対し上記特約違反について抗議しようとしていた所、Cが上記100万円の売買代金の請求をしてきた。この場合、BはCの請求に応じなければならないかについて記述せよ
(人の生命または身体を害するものでない)不法行為による損害賠償請求権は、被害者又は法定代理人が、いつの時点から何年間行使しないときに消滅するか2つの場合を記述せよ
A市は、A市路上喫煙禁止条例を制定し、同市の指定した路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙した者について、2万円以下の過料を科す旨を定めている。Xは路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙し、同市が採用した路上喫煙指導員により発見された。この場合、Xに対する過料を科すための手続は、いかなる法律に定められており、また、同法によれば、この過料は、いかなる機関により科されるか。さらに行政法学上、このような過料による制裁を何と呼んでいるか。
民法の規定によれば、離婚の財産上の法的効果として、離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することが出来る。判例は、離婚に伴う財産分与の目的ないし機能には3つの要素が含まれ得ると解している。この財産分与の3つの要素について記述せよ