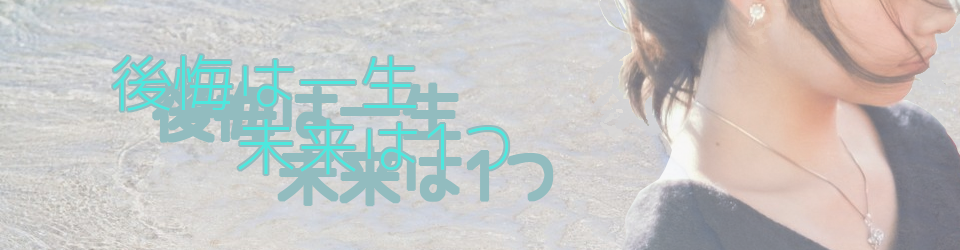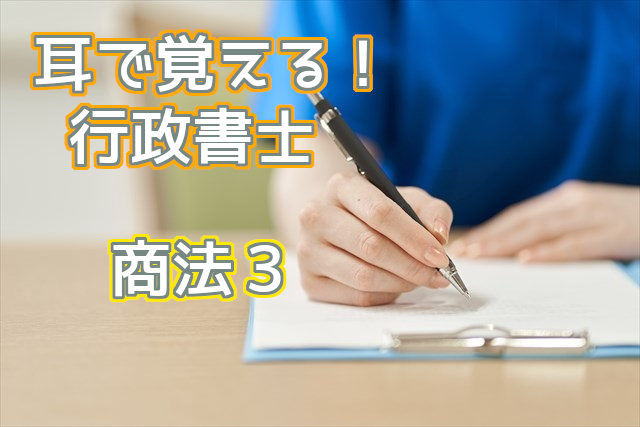※重複する過去問がある場合があります。
ここからチャンネル登録できます。商法
商事に関してはまず商法の規定が適用されるが、商法に規定がないときは民法が適用され、民法の規定もない場合は商慣習法が適用される。
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、自己を営業主と誤認して取引を行った者に対して、当該取引から生ずる債務についてその他人と連帯して弁済しなければならない。
商号は営業とともに譲渡する場合のほか、これを譲渡できない。
支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有し、支配人の代理権に加えた制限は、それを登記した場合に、これをもって善意の第三者に対抗することができる。
支配人は、商人の許可がなければ自ら営業を行うことができないが、商人の許可がなくとも自己または第三者の為に商人の営業の部類に属する取引を行うことができる。
商法上の代理商とは、一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理又は媒介を行う独立した商人である。
商業使用人を用いる場合は自然人でなければならないが、代理商を用いる場合は法人でもよい
Aは、その営業の地域を拡大するのに、支店を設け、商業使用人を用いるか、土地の事情に通じた代理商を用いるかについて検討したところ、商業使用人のうちの支配人も、代理商も、Aの営業に属する取引を自己または第三者のために行う事は出来ない。
取引所でなされる行為であっても、商人以外の者がこれを行ったときは商行為とはならない。
場屋取引とは、客に一定の設備を利用させることを目的とする取引であり、営業としてこれを行う時は商行為となる。
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申し込みを受けた者が遅滞なく承諾の通知を発しなかったときは、その申し込みはその効力を失う。
商人が平常取引をなすものからその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく契約の申し込みに対する諾否の通知を怠ったときは、その商人は当該契約の申し込みを拒絶したものとみなされる。
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申し込みを受け、申し込みとともに受け取った物品がある場合において、その申し込みを拒絶する時は、相当の期間内にその物品を相手方の費用により返還しなければならない。
数人の者がその一人または全員の為に商行為となる行為により債務を負担したときは、その債務は各自が連帯して負担する
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
当事者一方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は債権の弁済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の物または有価証券を留置することができる。
匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、その営業から生ずる利益を分配することを約する契約である。
匿名組合員は、信用や労務を出資の目的とすることは出来ず、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
商法上の仲立人とは、他人間の商行為について、代理または媒介をなすことを生業とするものである
商法上の問屋とは、自己の名をもって、他人のために物品の販売または買い入れをすることを業とする者である
運送人は、運送品の受取から引渡までの間にその運送品の受取、運送、保管及び引渡しに関して注意を怠らなかったことを証明するのでなければ、その運送品に生じた損害を賠償する責任を負う
運送品が高価品であるときは、荷送人が運送を委託するにあたりその種類および価額を通知した場合を除き、荷送人は運送品に関する損害賠償責任を負わない
商人がその営業の範囲内において物品の寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもってその物品を保管する義務を負う
場屋営業者は、客から寄託を受けた物品について、物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明すれば、その物品に生じた損害を賠償する責任を負わない
客が特に寄託しない物品であっても、客が場屋内に携帯した物品が場屋営業者の不注意によって損害を受けたときは、場屋営業者はその物品に生じた損害を賠償する責任を負う
場屋営業者が寄託した物品が高価品であるとき、客がその種類および価額を通知してこれを場屋営業者に寄託したのでなければ、場屋営業者はその物品に生じた損害を賠償する責任を負わない
両当事者の一方にとって商行為である行為については、もう一方の当事者についても商法が適用される
自己の名をもって商行為をなすことを業とする者以外には商法において商人性を認めていない
※コトバンク参考
未成年者は商法上の商人となることができない
未成年者は、商法上の商人として営業を営むためには登記をしなければならない
個人商人が複数の営業を営む場合には、その営業ごとに複数の商号を使用することができるが、会社は1個の商号しか使用することができない
商号は、営業上自己を表示するために用いられるものであるから、文字だけでなく図形や記号をもって表示してもよい
商号の使用は会社企業に限られ、会社でない個人企業は商号を用いることはできず、その名称は企業者個人の氏名を表示しているにすぎない
不正の目的をもって他人の営業と誤認させる商号を使用する者があるとき、これによって利益を害されるおそれがある商人は、自らの商号について登記がなくてもその使用の差止を請求することができる
商号を選択し登記した商人は、利益を害せられるおそれのあるときは、不正の目的をもって当該商号選択者の営業と誤認させるような商号の使用行為の差止を請求することができるし、商号不正使用者は過料にも処せられる
商号の譲渡は、その登記をするのでなければ商号譲渡の効力は生じない
営業譲渡において譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合は、譲渡人の営業によって生じた債務については、譲受人は譲渡人と連帯してその弁済をしなければならない
商人の営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は、その事項に関して一切の裁判外の行為をする権限を有し、当該使用人の代理権に加えた制限は、これをもって善意の第三者に対抗することができない
物品の販売を目的とする店舗の使用人は、相手方が悪意であった場合も、その店舗にある物品の販売に関する権限を有するものとみなされる
Aは、その営業の地域を拡大するのに、支店を設け、商業使用人を用いるか、土地の事情に通じた代理商を用いるかについて検討する場合、商業使用人はAに従属しその商業上の業務を対外的に補助するが、代理商はAから独立しAの企業組織の外部にあって補助することになる。
Aは、その営業の地域を拡大するのに、支店を設け、商業使用人をもちいるか土地の事情に通じた代理商を用いるかについて検討する場合、Aとの契約関係は、商業使用人の場合は雇用関係であり、代理商の場合は委任または準委任契約になる
取引に関する代理権は、商業使用人の場合は制限したり授与しないこともできるが、代理商の場合は必ず授与しなければならない
手形その他の商業証券に関する行為は商行為とされる
電気またはガスの供給については、その行為者および行為の態様を問わずすべて商行為とならない
商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを契約で定めることができる
匿名組合員による出資は、組合の財産を形成することはなく、営業者の財産に属する
匿名組合員は、営業者の業務を執行し、または営業者を代表することはできない
運送人は、荷送人の請求があるときには送り状を作成し、荷送人に交付しなければならない
運送品がその性質又は瑕疵によって滅失又は損傷したときは、荷送人は運賃の支払いを拒むことができる
商法にいう高価品とは、単に高価な物品を意味するのではなく、運送人が荷送人から収受する運送賃に照らして著しく高価なものをいう
荷送人が種類および価額の通知をしないときであっても、運送契約締結時、運送品が高価品であることを運送人が知っていた時は運送人は免責されない
運送人の故意によって高価品に損害が生じた場合には運送人は免責されないが、運送人の重大な過失によって損害が生じた時は免責される
客が携帯する物品について責任を負わない旨を表示した場合には、場屋営業者は損害賠償責任を負う事はない
会社法
株式会社の資本金額は、利害関係人にとって唯一の責任財産となるから、定款に記載・記録されると共に、登記および貸借対照表により公示・公告される
株式会社の定款には、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額を記載又は記録しなければならない
募集設立の場合、発起人以外の者が設立に際して発行される株式の全部を引き受けることができる
発起設立又は募集設立いずれの場合でも、各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない
金銭以外の財産を出資する場合、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載又は記録しなければ、その効力を生じない
会社の設立に際して、発起設立または募集設立のいずれの方法による場合も、創立総会を開催しなければならない
会社の設立に際して現物出資を行うことができるのは発起人のみであるが、財産引受については、発起人以外の者もその相手方となることができる
設立に際して発行される株式については、その出資に係る金銭の全額の払込みおよび現物出資の目的となる財産の全部の給付が必要である。
発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗することができない
会社設立時に株式会社が発行する株式数は会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の1/4を下回ることができないため、定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが、会社法上の公開会社でない会社の場合には、発行株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めを置かなくてもよい
会社の設立にあたって、公開会社の場合には、発行可能株式総数の全部を発行することは必要ではなく、その1/4以上を発行するだけでよい
株式会社は、株主総会による決議をもって初めて法律上成立する
発起人は、その出資に係る金銭の払込みを仮装し、またはその出資に係る金銭以外の財産の給付を仮装した場合、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払い、または給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部を給付する義務を負う
発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対してこれによって生じた損害を賠償する責任を負う
発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う
株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は連帯して、株式会社に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する
設立時募集株式の引受人のうち出資の履行をしていないものがある場合、発起人は出資の履行をしていない引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない
発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人または設立時募集株式の引受人による払込みの取り扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる
設立時取締役その他の設立時役員等が選任されたときは、当該設立時役員等が会社設立の業務を執行し、またはその監査を行う
出資の履行により設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗できない
株式の譲渡は投下資本の回収を図る手段であるから、株式の自由譲渡性が認められなければならないため、株式の内容として、譲渡によるその株式の取得について会社の承認を要する旨を定款で定めることはできない
株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることを定めることができる
株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定めることができる
株券発行前の株式の譲渡は無効となる
すべての株式会社は、株主名簿を作成し、株主の氏名または名称および住所ならびに当該株主の有する株式の種類および数などを記載または記録しなければならない。
株式の譲渡は、取得者の氏名又は名称および住所を株主名簿に記載・記録しなければ株式会社に対抗できない
株券発行会社において、株式の譲受人は、株主名簿の名義書き換えをしなければ当該会社および第三者に対して株式の取得を対抗できない
株式会社が、株主総会の決議に基づいて、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる
株式会社がほかの会社の事業の全部を譲り受ける場合には、当該株式会社は、当該ほかの会社が有する当該株式会社の株式を取得することができる。
株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない
株式の分割を行う場合には、株主総会の特別決議によるその承認が必要である
株主総会決議に反する株主が買取請求権を行使するには、原則としてその決議に先立ち反対の旨を会社に通知し、かつ、その総会において反対しなければならない
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる
公開会社である取締役会設置会社が企業提携のために、特定の第三者に対して募集株式を時価発行する場合には、取締役会の決定で足りる
募集新株予約権の発行が法令もしくは定款に違反し、または著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときには、株主は、会社に対して募集新株予約権の発行をやめることを請求することができる
取締役会または監査役を設置していない株式会社も設立することができる
株主総会は、会社の最高意思決定機関であるが、取締役会設置会社において、その権限は法定事項と定款所定事項の決定に限定されている
取締役会設置会社においては、株主総会は、代表取締役がその招集を決定し、取締役会が招集手続きを行う
株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならず、臨時に招集することはできない
招集権者による株主総会の招集の手続きを欠く場合であっても、株主全員がその開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会において、株主総会の権限に属する事項について決議をしたときは、この決議は株主総会の決議として有効に成立する
合名会社と合資会社の持分は、定款の定めにより1持分につき複数の議決権を与えることができるが、株式会社でも1株に複数の議決権を有する種類株式を発行する旨を定款に定めることができる
株主は、株式総会ごとに代理権を授与した代理人によってその議決権を行使できる
株主は2個以上の議決権を有するときはこれを統一的に行使しなければならない
会社は、自己の株式を所有している場合は株主総会においてその株式について議決権を有しない
会社は、自己の総株主の議決権の1/4を超える議決権を他の会社に保有させている場合には、その会社の株式を有していても、その有する株式についての議決権を行使できない
株主総会の決議につき、特別の利害関係を有する株主はその決議に参加することができない
株主総会の決議事項に関して取締役または株主から提案がなされ、当該決議事項について議決権を行使することができる株主の全員が書面または電磁的記録によりその提案内容に同意した場合は、実際に会議を開催しなくても、その提案を可決する株主総会の決議があったものとみなされる
取締役は、株主総会において選任することとされているが、定款に規定することにより取締役会において選任することもできる
すべての株式会社は、定款において、取締役の資格として当該株式会社の株主である旨を定めることができる
監査等委員会設置会社においては、3人以上の監査等委員である取締役を置き、その過半数は社外取締役でなければならない
取締役の任期はいかなる場合でも2年を超えることができない
公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社であって金融商品取引法所定の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものであっても、社外取締役を設置する必要はないが、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない
取締役会設置会社において、取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行う場合には、取締役会において当該取引に関する重要な事実を開示して、その承認を受けなければならない
取締役会設置会社の代表取締役Aが、取締役会の承認を得て会社から金銭を受けた場合であっても、Aは、事後にその貸付に関する重要な事実を取締役会に報告しなければならない
取締役会設置会社において、取締役が、取締役会の承認を受けて会社を代表して他の取締役に金銭を貸し付けた場合であっても、その取締役はまだ弁済のない額について弁済する責任を負う
取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う
取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができない
取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する
取締役会設置会社の代表取締役Aが、取締役会の承認を得て、会社から金銭の貸付を受けたが、Aが金銭の返済を怠った場合には、取締役会での金銭の貸付を承認した他の取締役はAと連帯して会社に対して損害賠償責任を負う
公開会社において、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、6か月前から引き続き株式を有する株主は、会社の為に取締役に対しその行為の差止めを請求することができる
株主総会の召集の決定など、法律により取締役会が決定すべきものとされている事項についても、定款の定めによって代表取締役に決定権限を委譲することができる
指名委員会等設置会社の業務を執行し代表権を有する執行役は、指名委員会が指名する候補者の中から株主総会で選任される
会社が指名委員会等設置会社である場合、取締役会決議により、多額の借入の決定権限を執行役に委任することができる
監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社はいずれも取締役会設置会社である
監査等委員会設置会社を代表する機関は代表取締役であるが、指名委員会等設置会社を代表する機関は代表執行役である
株式の払込み額の2分の1を超えない額については、資本金として計上しないことができ、計上しないこととした額は資本準備金としなければならない。
会社が自己株式を有する場合、株主とともに当該会社も剰余金の配当を受けることができるが、配当財産の額は利益準備金に計上しなければならない
取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り、取締役会決議により剰余金の配当(中間配当)することができる旨を定款で定めることができる
剰余金の配当により株主に交付される金銭等の帳簿価額の総額は、剰余金の配当が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない
合併の各当事会社は、会社債権者に対して、合併に異議があれば一定の期間内に述べるよう官報に公告し、かつ電子公告をした場合であっても、知れている債権者には個別催告する必要がある
持分会社の無限責任社員は、株式会社の株主とは異なり、金銭出資や現物出資にかぎらず、労務出資や信用出資の方法が認められている
合名会社の社員は原則、会社の業務執行権および代表権を有する
合資会社では、無限責任社員から業務執行権と会社代表権を有する代表社員を選任することを要し、株式会社における取締役会設置会社では、取締役から業務執行権と会社代表権を有する代表取締役を選任する
持分会社は、会社法上の公開会社である株式会社とは異なり、原則、社員各自が当該会社の業務を執行し、当該会社を代表する
わが国では、商人の利益保護の観点から商号自由主義が採用されているので、商人は商号の選定につき制限を受けることなく自由に選定できる